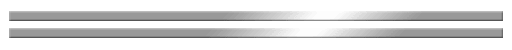
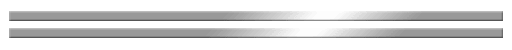
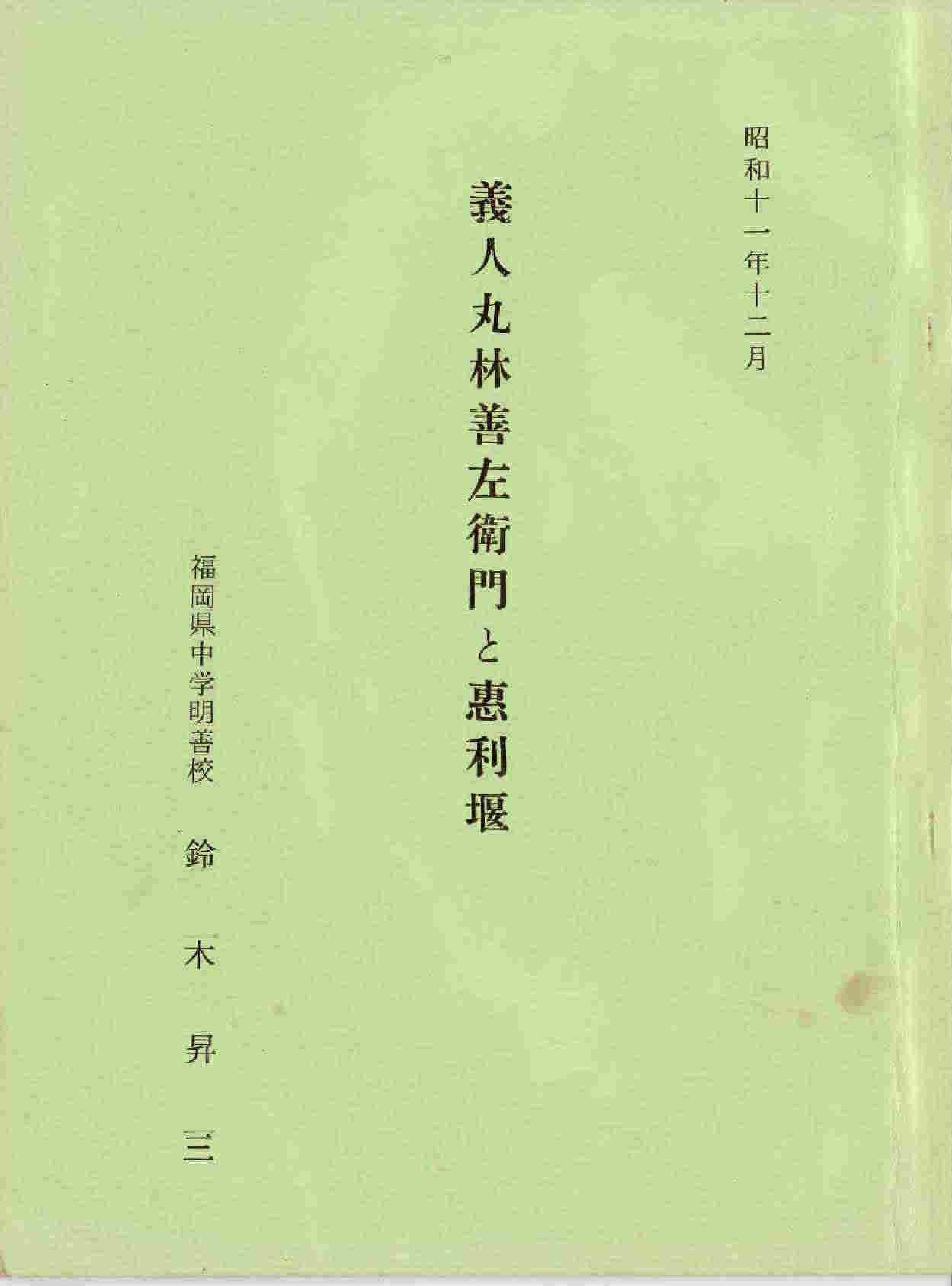
昭和11年12月
義人丸林善左衛門と恵利堰
福岡県中学明善校 鈴木昇三
義人丸林善左衛門と恵利堰
鈴 木 昇 三
二千数百年の昔、ギリシャの大史家ヘロドッスは「埃乃文明はナイル川の賜なり」と喝破した。
流石歴史の父と言われた彼らしい観察である。
我が筑後、特に浮羽、三井、三瀦、久留米の郡市を考えた時、その産業は勿論、交通、運輸、政治、軍事、文化等一として筑後川の影響、お蔭を受けないものは無い。真に筑後の文明は筑後川の賜なりと云うべきである。しかし今はその一つ一つについて影響を述べる紙数が許されぬ。それで只産業、しかもその中の米についてのみ記する事にする。
我が国の米を考えた時、我が県が如何程重要な地位を占めて居るかは、誰でも知っている。新潟県に次いで全国府県中第二位を占める年が多い。県の調査によると、昭和八年度総額五千五百四十二萬千三百十一円となって居る。その中で浮羽郡が二百六十一萬七千二百八十七円、三井郡が三百七十四萬三千五百六円、三瀦郡が四百八十七萬七千百二十九円で、此の三郡即ち筑後川沿岸の産額は合計千百二十三萬七千九百二十二円となる。県下十九郡中僅か三郡の産額が県下総額の約二割二分に当って居る。以て筑後川沿岸三郡の県下米産上の地位、延いては全国米産額上の重要地位が明かとなるであろう。そしてこの三郡は大体筑後川の灌漑によると考えて大した間違いは無い。更に朝倉郡と佐賀県下の米産を考えた時、筑後川の米産に与える利益だけでも測り知れないものがある。
しかし最初から楽々と、此の川の水が田に引かれるようになって居た地方は少なかった。地が川面より高くて折角豊饒な土地を持ちながら、藪や林や畑として放棄せねばならなかった所が多かった。地と涙と汗、否生命を抛げ出して、生きんがために我が筑後の偉人、先覚者が苦心惨胆の結果今日の田としてくれたのだ。それを我々が今御蔭を蒙って居る。又子孫は永久に恩沢に浴するのである。その心血が今日浮羽郡獺の瀬堰、袋野匿溝となり、大石長野の堰梁となり、朝倉郡山田堰梁となり、三井郡恵利堰(床島堰)等となったのである。近頃国利民福、殖産興業という言葉が多く用いられて是等先覚者の偉業を此の言葉で片づけて仕舞う人も居るが、是は断じて五庄屋や、田代重栄や、丸林善左衛門、高山六右衛門等の精神を研究したとは云えない。彼等偉人はそんな生温い、或いは功利的な考えからやったのでは無い。もっともっと深刻な死せんとする村民を救わんとの大犠牲心から生命を抛って奮い立ったのである。まことに決死の大勇猛心の発露である事を断言して少しの誤りも無いと確信する。
浮羽郡獺の瀬堰、袋野匿溝、大石長野堰溝は幸い古記録が、明らかにせられて居るが、三井郡の恵利堰については不明な所もあり、特に丸林善左衛門の大犠牲心は知られて居らない点が多い。常々それを残念に思って居たが今年夏休中古い記録を探し出したので、それを基にして書いて見た。それで私の主眼とする所は恵利堰や、草野又六、高山六右衛門、秋山新左衛門、中垣清右衛門、鹿毛甚右衛門の事跡を述べる事ではない。是等は今まで一通り調べられ、世人にも知られて居る。丸林善左衛門は前記五人、特に高山、秋山、中垣、鹿毛、四庄屋とは大分趣を異にしている。それに今まであまり知られて居らぬ。私の特に重点を此の大義人に置いたのはその大犠牲心を一人でも多く知ってほしい念願からであり、又出来るだけ明らかにする事が筑後に住んで居る私の務めだと思ったからである。
(一)丸林家と古文書
丸林家は浮羽郡芝刈村早田にある。早田村代々の庄屋で此の地方人の尊敬は甚だ厚い、今は早田の戸長をして居られる。同家の「竹野郡早田村庄屋先祖代々名附」には次のように記されて居る。
一、慶長元申年より元和七酉年迄 庄屋源四郎
弐拾六ヶ年相勤申候
一、元和七酉年より寛永弐拾未歳迄 庄屋源四郎倅
二十三ヶ年相勤申候 市兵衛
一、寛永弐拾未歳より正保元申年迄 庄屋市兵衛倅
弐ヶ年相勤申候 善左衛門
一、正保元申年より宝永元申年迄 庄屋善左衛門倅
六拾一ヶ年相勤申候 久兵衛
一、宝永元申年より正徳元卯年迄 庄屋久兵衛倅
八ヶ年相勤申候 善兵衛
一、正徳元卯年より享保十三申年迄 庄屋善兵衛倅
拾八ヶ年相勤申候 善左衛門
一、享保十三申年より宝暦三酉年迄 庄屋善左衛門倅
弐拾六ヶ年相勤申候 善六
一、宝暦三酉年より享和元酉年迄 庄屋善六倅
四拾九ヶ年相勤申候 善兵衛
一、享和元酉年より文政元寅年迄 庄屋善兵衛倅
拾八ヶ年相勤申候 善六
一、文政七申年より嘉永五子年迄 庄屋善六倅
弐拾九ヶ年相勤申候 善治
一、嘉永五子年より当午年迄 庄屋善治倅
拾九ヶ年相勤申候 久右衛門
〆是迄弐百七十五年
右之通書上申候
明治三午年五月
是は久右衛門という人が昔から家に伝わる系図や記録を基として明治三年に整えて書いたものだが、同家他の古記録や他家の記録とも合って居るから大体間違いはないと思ってよい。此の外同家には丸林家のものや早田村に関するもの等夥しい文書が保存されて居る。今は、ぼろぼろ、ばらばらになって読み難いものもある。その中には更に最后の庄屋久右衛門の代になって書き写して帳に纏められて居るものもある。達筆であるが、我流の崩し方や、誤字や、当て字が相当ある。被と罷と取や、者と共と江とより など不分明な所など多い。
是等の古文書中恵利堰溝一件に関する主なものは次の通りである。
(1)堰地方の古地図四枚(中に裏へ正徳二年辰絵図、宝暦弐年申四月八日是を改む、庄屋善六、 久右衛門、絵師清次郎と書いたものが一枚ある)
(2)井堰下並船通左右野方の儀に付御願奉申上書附
(3)井堰且中曽一件之儀品々書付
(4)床島井堰御仕立前後品々控帳
(5)正徳四年午十月二十七日田畑春免御定
(6)元禄十年丑二月水帳
(7)寛永二十二年申正月高畝数名名寄帳
(8)慶長元申年六月水帳 畠方居屋敷並藪畝全
(9)慶長六年八月九日御検地帳
久右衛門の次が十三次氏(大正十三年卒)、次が当主十四次氏(明治十八年生)で、早田の戸長を始め芝刈村の色々な名誉職をして居られる。
(二)恵利堰(床島堰)
話の順序としてどうしても恵利堰の事に触れねばならぬ。此の堰は普通床島堰と云われて居るが、是は後に述べるように、昔は筑前を憚って称したものだが、所在地は床島でなく恵利だから今は当然恵利堰と称すべきである。又床島の新川にも小さい堰があるから紛れやすい。
此の堰は今から二百二十四年前、中御門天皇の正徳二年(徳川家宣将軍時代)に築かれたものだ。
丸林家文書には次の様に記されて居る。
竹野郡床嶋堰所用水新溝出来覚
一、御井郡弐拾八ヶ村古田旱損地天水所多及難儀且又畑方水損所多為困窮候ニ付床島村東藪際早田村分水道仕立新溝被仰付被下候者新畑田出来古田旱損茂無之耕作取続申度段宝永八卯春依願溝筋見積書付持出重々御吟味之上竹野郡田主丸六郎?左衛門と申者曲尺見申候処弥水乗宜畑田作七百町余出来入用銀目録他(或いは作?)五拾貫目余拝領人夫惣御郡ニ被仰付被下候様願出候同秋正徳元卯十月十四日願之通被仰付入用材木拝領造用銀拾三貫五百目拝領被仰付翌辰二月廿一日ヨリ惣御郡夫ヲ以御普請被仰付同五月迄大概御普請相仕過古田畑田並ニ根付仕候
但井堰百七十間恵利瀬形石組長百間
右件借銀享保十二未年ヨリ 年迄五ヶ年 ニ而返納仕候
一、右堰所入用多溝下中年々及不申候ニ付江戸水道所ヨリ上床嶋堰所迄惣御郡役ニ被仰付候
一、右新溝口願場所下リ水乗不足ニ付床嶋村下筑後川筋堰立被仰付候
一、恵利瀬形船通在之候而者水乗悪敷候ニ付正徳四午年船通堰留旱田浜筑前境ニ川堀○(壱字不明)床嶋村堰所之上唯今の場所船通被仰付候(是は次の(三)恵利瀬の増築に関するもの)
一、右堀鑿之場所筑前御領境少々流通石船往来筑前より相妨候ニ付恵利瀬古川筋築留〆只今之川筋ニ罷成早田浜全ク当御領ニ相極リ候(是も(三)恵利瀬の増築に関するもの)
一、床嶋堰所恵利瀬形石組之儀享保九辰年ヨリ‥‥‥(省く)
一、享保二十卯年七月(省く)
一、右用水引受候村数
御井郡
守部村 八重亀村 高嶋村
赤司村 山須村 稲数村 仁王丸村 塚嶋村
陣屋村 中村 今山村 十郎丸村 高良村 鳥巣村 石崎村
上弓削村 下川村 江戸村 染村 安永村
御原郡
今村 下高橋村
総而 弐拾八ヶ村 本願
御原郡
御井郡
古賀村 八丁嶋村 鷹鳥之須村 森村 五郎丸村
〆拾ヶ村 後願(此の分は不正確)
合参拾八ヶ村
一体筑後川の北岸の旧三井、三原二郡は土地は広くて地味も肥え其上川にも近いのに川面よりも高いので久しく荒れ地のまゝで所々に田地はあっても一に雨水を待つと云う状態であったから五穀は収穫少なく、不幸にして旱天年となれば居民は忽ち飢餓に逼られ四方に流離する者が多かった。それで各村共年々疲弊するばかりであったが霊元天皇の寛文四年(徳川家綱将軍時代)彼の有名な五庄屋によって大石長野の堰が造られた。是にならって一大堰溝を開きたいとの意見は、此の地方各村庄屋にあったが、浮羽郡大石よりも約五里の下流に当たり、川幅も広く、水勢は荒くその上此の地は筑前黒田領と筑後有馬領との境であり下手な事をすれば一大紛擾を起す恐れがあるので、率先して工事に当たろうとする者もなく、延び延びになって居たが遂に
宝永七年の春またもや大旱魃で村民の流離する者が、甚だ多くなった。六右衛門は最早猶予すべきでない是非共筑後川の水を引く工夫せねばならぬと考えた。幸い久留米藩の目付遠山氏の隠居六郎左衛門の尽力によって、郡総裁本荘主計同市正父子を動かし、本荘父子の情によって、家老の内諾を得た。喜び勇んだ六右衛門は、高嶋村庄屋甚右衛門父子を訪うて、互に決死の覚悟で事に当る事を誓い、公儀向の事は六右衛門、金銀物入の儀一切は甚右衛門と分担を定めた。
更に稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門等各村庄屋も加わって、堰溝築開の願書の調製に着手した。
時に宝永七年八月であった。其願村は
御井郡(今三井郡)
守部村(現大堰村の中) 江戸村(大堰) 下川村(大堰) 八重亀村(現金島村の中)
高嶋村(金島)
稲数村(大城) 仁王丸村(大城) 塚島村(大城)
高良村(弓削村の中) 鳥巣村(弓削) 石崎村(弓削) 上弓削村(弓削)
御原郡(現三井郡)
今村(現太刀洗村の中) 下高橋村(太刀洗)
計二十八ヶ村
しかしいざ願書提出という時になって、何故か上弓削、江戸、染、下川、安永、今、下高橋七ヶ村は之に加わらなかったので残二十一ヶ村が連判した。六右衛門はこの願書を、郡奉行国友覚右衛門に提出したのは、宝永七年十月二十日であった。
今その設計の大要を見ると
一、筑後川を恵利瀬の所で堰き止め其一部に水餘を造り、之を舟通しとすること
二、堰の北岸から床島に向けて、一大溝を造り河水を之に導くこと
三、床島に水門を設け其水門から吸取する水は、溝に流れて千二百余間下の江戸前に至り、此処から漸次派を分けて、三十余村の田地を灌漑する
四、新溝開通の暁には、古田の灌漑は勿論、別に藪林畠を開墾して、七百余町歩の新田を得る見込あること
五、従来は上納米も不足勝であったが此の工事完成の上は、米大豆差引一ヶ年、約七千俵の増米ある見込であること
六、築造費は銀五十貫目を要すること
七、此築造費五十貫目は藩から借用して年賦で返済すること
八、人夫はすべて郡役にすること
九、水道に入用の材木は手寄りの官山から拝領すること
十、領内の石のみで不足する恐れあるから他領から購入する
十一、小石を運搬するため船二十五隻を要すること
十二、岩並に割石は御井、山本両郡の内手寄りの山から拝領する
十三、大工、木挽、杣取の前賃銀其他諸品買入の為、銀子拾貫先ず借用すること
等となっている。
時の藩主は梅巌公則維で英明、治道に励精せられて居たので、願書を一覧せられ、大いに之を壮とし便宜を与えよとの沙汰があった。
因って藩では工事監督として野村宗之丞、草野又六を遣わし、請うまゝに官林の伐採を許し、銀子も貸下げ、一挙にして工事に着手しようとした。
然るに此の事を伝聞した筑前領の諸村は驚いた。大川の中流を堰止め、恵利に水門を設けられては、其上流に臨んだ我が諸村は、洪水の際は残らず水底に沈むというので、川越六之丞という者十一ヶ村の庄屋の抗議書を持って、久留米藩に迫ってきた。久留米藩も躊躇して工事も沙汰止となった。各庄屋の煩悶は想像に余りある。鏡村庄屋六右衛門は必死の運動を藩に続けたが、此の上は神仏のお助けによる外はないと、高良玉垂宮に七日の断食をして祈願をした。神もその心事を憐れまれてか藩も大いに決する処あり、水道口を二十町程度引下げ、堤防も築かず、一歩筑前に譲って置いて断呼として工事に着手した。時に正徳二年正月二十一日。
此の時の請負奉行は野村宗之丞で、総取締が草野又六である。
中にも草野又六は中心人物として、最も重きをなし工事の大部分は彼の力によるものとさえ云われて居る。彼は山本郡大橋村の鹿毛宗五郎の二男で、同郡草野村の草野五左衛門の養子となった。天性剛毅果断、胆力人に超え水利墾田の術に長じて居たので、抜擢せられて下士となり、土を開き利を興した事、前後幾回なるを知らぬ。又親に仕えて至孝、智あり、涙あるの士であった。
斯くて正徳二年正月二十一日から毎日三千五百人宛の人夫を指揮し、堰所、溝筋とも同時に工事に着手した。堰の長さは百七十間、筑後川でも此の辺は名に負う奔流急湍であるから其の水を遮断すべく築成するには非常な困難であった。一体獺の瀬堰も大石の堰も、山田の堰も恵利の堰も、非常な難工事である。それは一見すれば明らかである通り、第一どの川でも堰は其処で水準を不自然に一時高めて、川面より高い地へ水を導くのだから、最初から勾配のあるところへ築かねばならぬ(平々坦々とした所へ築いても用をなさぬ)。従って急流へ築造する事になるから難工事は初めから覚悟の前だが、筑後川は全国屈指の大川で、水量が多く、川幅は広い。さればこそ是等四堰は全国堰中の難工事と呼ばれて居るのだ。殊に恵利は最も下流であるから上流三堰に比して、水量も多く、川幅も広いので如何に苦心したかという事は素人の我々でも直感する。今日川下から此の大堰を見上げた時何等文明の利器を有せぬ徳川中期、よくも人力のみで造ったものだと驚歎の外はない。
如何に、大木、大石を投込んでも、木の葉のように推流されるので流石の又六も術の施し様もなく、失望の余り家に帰って、殆ど病人となった。処が其母は又余程の賢夫人で又六を門前に呼び出して、仰いで水縄の連山を指して、彼を見よ、あれだけの土や石があるではないか、高の知れた筑後川、何の填まらぬ事があるか、と励ました。又六聞いて奮起し、石小石を数隻の古舟に積み船と共に沈めたので、やっと基礎を固める事が出来た。更に近くの山から数十万の大石を運んで来て、小石は別に俵に詰めて五十万俵を作ってそれを一時に沈めた。
それでやっと河水は堰かれて新溝に入った。しかし水門は筑前領の抗議によって当初の設計を変更して新溝口から約三十六町下の江戸前という所へ弐個設けた。
こうして堰と溝とは大体三月中頃には出来上ったが、恵利堰は急ぎの工事で洩水が多く新溝に流れてくる水量が、予期したよりも少ない。更に
(三)恵利堰の増築
出来上がった恵利堰を見ると、船通しがあって堰の一部が開放せられているので、多量の筑後川の水はこゝから流れ去って新溝へは十分注がぬ。それで各村の用水は不足であるのにその上御原郡の平田、小島、上高橋、甲条、鵜木、古賀、八町島、恋之坂、森、五郎丸の十ヶ村が配水を懇願して来たので、之を許すと合わせて三十八ヶ村となり、水は益々不足する。それで藩は正徳四年堰の改築を企てた。此の度の上奉行は田山善兵衛で、普請奉行は野村宗之丞で、総裁判は草野又六である。又六は先ず恵利堰の船通しを閉塞して百余間の石堰を増築しようと計画した。所が其の中程に竹野郡(現浮羽郡)早田村分で中曽、吉原という所がある(現今は中洲といって島形をなし御井郡分となって居る)。此の地は筑前領下座郡長田村と接して、久しい間荒蕪地となって居て其の境界は殆ど不明であった。筑前長田村の民は又六の計画を聞いて之は一大事、もし恵利堰の船通しを閉鎖されては河水は停滞して、長田村の土地は甚しく湿潤となり、耕作を害し、殊に洪水の時は多大の惨害を蒙るし、船で筑後川を上下する時の不便は大となり、また黙って居ては中曽吉原は明らかに筑後領となってしまう。以上の諸理由によって中洲は筑前領であると唱え、筑後の作業船の通路に乱杭を打込んで工事の妨害を始め、遂には石堤を突出し水勢を激せしめ筑後早田村の沿岸に流潟して来た。よって筑後の諸庄屋は憤激する。又六は長田村の庄屋にそれを取除くよう申込んだが、問題は容易に解決せぬ。又六も頗る躊躇した。此の時早田村の庄屋善左衛門が進み出て此処は昔から早田村の分である。他人は何と云っても此の庄屋の自分が知って居る。遠慮は御無用、早く工事を開始するがよろしいと、意気昇天の概があった。此の一言によって又六も励まされ、一日に人夫二千人宛も召集して一斉に手を下し、先ず船通しを新たに中曽に開掘し船は筑後川から新川に入り、此の船通しを過ぎて再び筑後川へ出るようにした。
恵利堰の船通しへは大木、巨石を積み沈めて堰止め、深く筑前領の岸陸に沿うて、新川と称する水路を通したので、筑後川の水は多く此の新川から溝に入り、水量は甚だ豊富となった。今行って見ると溝でなく川だ、しかも甚だ深くて恐ろしい位だ。
恵利の石堰は先年築いた分と合わすと、長さ二百七十間、新川の捨石の所まで加えると、五百間近くもある。堅牢無比、人間の作ったものとは思われぬ。筑後川の一偉観である。
(四)義人早田村庄屋善左衛門
此の工事中であった。筑前長田村から大勢の人足が来て、手当り次第に礫を投げるので、筑後の方も亦応戦して双方入り乱れて正に一大惨事を起こそうとした。その中筑前方から風彩の賤しからぬ者十余人、長田村の百姓と名乗って草野又六の前に出て、此処は筑前領である、何故に掘立つるかと詰問した。此の時筑後早田村の庄屋善左衛門が進み出て、それは役人方の知る処では無いから役人方に対して粗暴な振舞あってはならぬ。又自分先祖の代から庄屋として何も彼も委しく知って居る。此処は早田村分に相違無い、と述べたので筑前方はさらば今少し相尋ねる次第があると云って善左衛門を長田村へ連れて行こうとした。筑後の人夫はやらぬと抵抗する。しかし善左衛門は制して、ともかくも行って理非を明かにして来る、工事は中止するに及ばぬとて単身虎穴に飛込んだ。彼は一命を捨てて先方に行って掛合い、筑前領の者の注意を一身に集め、その暇に恵利堰の工事を急がせようと考えたもので、真に犠牲的大勇猛心の極度を現したものだ。此の精神こそ日本魂の真髄と云うべきである。
さて善左衛門を連れ去った十余名の者は長田村の百姓と云ったが、皆福岡藩士であったとの事で、善左衛門は三箇月余りも、番卒を附けられ大勢の者で境界の事を吟味して、昼夜厳しく責立てたが、彼は少しも屈する色なく前言を固持して中曽吉原は筑後早田村なりと言明するばかりで、とうとう筑前の連中も持て余し、善左衛門を引取ってくれと筑前徳淵村大庄屋から、竹野郡塩足村大庄屋へ申込んで来た。塩足村大庄屋は今が困らせ時と云うので、一旦連れて行った者であるから、お前の方で勝手に取扱ってくれと、はねつける。筑前方はいよいよ持て有す。其の虚に乗じて、昼夜兼行で工事を取り急いだので、恵利堰の増築は竣工した。
善左衛門は私かに御井郡稲数村の庄屋清右衛門に頼み郡中の某家に引き取り暫く滞留して後村に帰ったが、筑前の拘留中呵責に遭って身体の自由を失い、遂に病死した。身を殺して仁を成すというが、その壮烈義烈武士も遠く及ばぬではないか、非常時に処する真の精神とは是ではなかろうか。唯そればかりでは無い。彼はその支配地三町歩をこの工事のために失った。又畠地六町歩を、中曽吉原へ新川を掘るために、荒地とされた。又床島の東に飛地のあったのも一町ばかり失った。そもそも早田村は筑後川の南にあって、竹野郡に属して居るのだ、北岸の御井郡に如何なる水道が出来ようとも何等の御蔭を受けるのではない。彼こそ他郡公益のため、一身一家を犠牲にしたのである。是程美しい、是程尊ぶべき行為があろうか。武士道が徳川中期に至って江戸町人気質となり、更に百姓気質となったと聞くが、我等はそれを遺憾なく善左衛門に於て見るのである。前に私が彼と、高山、秋山、中垣、鹿毛等の諸庄屋と少しく趣を異にして居ると云ったのは、こゝである。即ち四人の庄屋等は何れも皆己の村に水溝を掘るのであるから決死の働きをするのも或いは頷かれる点もあるが、善左衛門は、自分の村とは無関係の他郡河北の為に身は死し、一家は田地を失い以後非常な困窮に陥ったのである。今日三井郡恵利堰灌漑九ヶ村は、彼を神と祭っているのは当然中の当然で、その感謝は丸林家の子々孫々に及ぶべきであろう。
善左衛門の子の善六も亦父に劣らぬ義侠の士であった。宝暦二年早田村分の中曽の荒地に、櫨木の植付けを願ったが藩は大切な堰の所在地であるから、後で問題が起こっては、と云うので是を許さなかった。藩の処置は甚だ徳に背いたものである。しかし、善六は少しも怨まないのみならず、筑前領の者が、新川口に乱杭を打込み恵利水道に妨害を加えようとした時も、父の志を継いで身を猟師にやつし、夜中之を抜き取ること再三に及んで居る。此の親にしてこの子あり。私は丸林父子の事跡を調べて限りなき尊敬と感謝と、愉快を覚えた。以上丸林父子の事跡は丸林家の文書に委しく記されて居る。
茲に全文を載せる。
早田村庄屋善左衛門口上之覚
一、当月十八日早田川原川掘御普請被遊候に付彼場所より私罷出居候処に長田村より百姓大勢杖棒持参仕私え逢可申由申候所草野又六様御逢被成其後北野塩足大庄屋衆並に両与庄屋衆被出合何角差引有之候処早田村庄屋え申談義有之と申私え大勢取掛申候 然所私申候者早田村分之内川掘申候を長田村之内と被申候者いヶ様之訳ニ而被申候哉と申私村百姓中も人足之内居申候を呼出猶又堺目の義を可申披と存人足之内江呼入候を跡より大勢長田村之者共双方石打合私へ取掛右之人数に巻籠長田之方へ引参候迄ハ相詰居被申候役人中茂事さはかしく有之存知不被申候向岸ヲ引揚申候時右役人中見被請おいかけ川中迄入込被申候得者長田村岸上より大勢ニ而積立候石手ニ手ニ打申候 猶又此方よりも石打申候其間に巻籠候人数ニ而私ヲ長田村之様引参候 同村百姓惣吉と申者所引込申候而猶又大勢之百姓声々ニ申候者長田村之内早田村之内と申川掘候義いか様之覚に而掘候哉と申候に付私申候者早田村川原之内北ニ川原ヲ残し置川掘申候夫ニ先刻よりむたひに声々ニ被申候段難心得義ニ候と申候処何角ハ入不申候間あやまりヲ書被申下候はゝ早々帰し可申由申候 私申候者か様にけが等もいたし殊てあやまりヲ書可申様無之と申候得者大勢ニ而申候者先年其方へ長田村よりあやまり取被申候間此方江茂此上者心儘ニあやまりを書取可申候若あやまり書不被申下候はは棒はさみ可致と申棒ヲ以儀式をなし申候ニ付私申候者少しの役義等も相勤居申候拙者を各心儘ニ被致候上者いか様成行候共あやまりの義は決而成不申候と申候得者立寄居候人数も少ハしりそきしばし仕候得者又々大勢取巻強勢之仕形ニ而私手を取あやまり書申候様にと申候得共猶又書申義不罷成候と申候ヲ右之手ヲ痛メ書ヲそめ私手を取かゝせ申候彼者共申候者先達而之掘川も筑前御領分と書申候様ニと重々申候得共書申義難成由申候 然処ニ川端参候節百姓ニ長田村ニ而認候覚長田村彦三郎方江当置申候長田村百姓中申候者差引茂相済候間罷帰候様に申候ニ付私申候者むたびに口書を取被置今更罷帰り候様ニ被申候段近比難心得候其村庄屋彦三郎より対面仕其上ニ而わけニより罷帰可申と申候得者集り居申候者共大勢ニ而私手を取引立帰り候様にと申候 存知寄も候得共不及カ川端迄参候且又長田村惣吉所ヲ罷出候時者大勢ニ而御座候得共段々しりそき川端迄参候者ハ四人ニ罷成申候 右之四人者共川掘所迄被参候様に申候得者参候義成不申由申候其分ニ而私は弥中程迄帰り掛り候得者私方百姓中出向申候者其方義長田村江被引取いか様之了簡ニ而今更被罷帰候哉定而今日之様子御注進可有御座と存候間長田村まで参候様にと申候ニ付長田村右惣吉方迄参候得者惣吉所戸をせき居申候ニ付庄屋彦三郎方江参対面可仕由申候得者留守ニ而御座候と申候 彦三郎倅出合申候ニ付私申候者先刻大勢ニ而先罷帰候様にと申候ニ付川掘前迄参り候処私村百姓中出向申候者今日之様子御注進可有之と存候殊に長田村ニ而其方差引之品も不承候に付長田村より参り様にと申候間惣吉方へ参り候得者右之通戸をせき入不申候ニ付其方村役人之義に御座候御宅へ居可申候哉又は村江宿被申付候哉と彦三郎倅に申聞候 彦三郎倅申候者先刻は何右衛門所宿被成候と申候 私申候者当所惣吉方百姓中つれ越候故居申候と申 彦三郎倅申候者右御座下候はゝ彦三郎義も留守にて御座候間右惣吉方江案内之者相添可申候ニ付彼者所へ御出候様にと被申候に付私義も惣吉方へ居申候
一、一八日暮六ツ時平四郎と申者所より百姓拾人程ニ而同道仕連越申候 同二十日暮六ツ時迄居申候 番人昼者二人夜四人料理一汁二菜ニ而御座候
一、同廿日暮時時分ヨリ金作と申所より百姓中七八人程ニ而同道仕連越申候 廿二日暮時分迄居申候 番人料理右同断
一、同廿二日暮時分より平四郎と申者所より七人程ニ而つれ越申候 番人料理等右同断ニ而廿四日迄居申候
一、同廿四日暮六ツ時分筑前御領鵜木村庄屋七郎江私宿平三郎方へ参被申候者筑後御領八重亀村庄屋新左衛門 今山村庄屋助次郎 稲数村庄屋喜右衛門 徳淵村触(?)口源左衛門方江右三人被参候 差引等茂大形相済申候間御自分義ハ白鳥村迄私同道仕筈ニ而迎ニ参候と被申候 私申候者御苦労ニ存候 乍然北野組庄屋取計ニ而候哉塩足村庄屋衆も被参候哉と相尋申候へば鵜木村庄屋七郎次被申候は北野組庄屋之取計ニ而候由被申候 私申候は右三人北野組より被参候庄屋中も兼而名は承居申候と申 白鳥村迄私儀茂同道可仕と申 七郎次同道ニ而廿四日暮六ツ時分長田村罷出申候 白鳥村の極に参申候処北野組八重亀村庄屋新右衛門 稲数村庄屋喜右衛門 今山村庄屋助次郎三人共々私逢申候者其方事被罷帰候様に仕くれ候様にと徳淵ニ而被申候得共只今之成行ニ而早田村之様ニ被罷帰義成不申塩足卯兵衛殿方江茂御受取有之間違候ニ付私共北野之様ニ致同道大庄屋善右衛門江預り被申候様に可仕と申談候間参候様にと被申候ニ付同日夜半八重亀迄参り泊り翌廿五日北野組中村之庄屋源右衛門迎に被参同道仕北野之様参り申候
右之通少も相違之義不申上候 以上
正徳四午年七月廿七日
竹野郡早田村庄屋 善右衛門
此の文は非常にごたごたして居て、字も疑問なのもあり、他の記録と一致せぬ所もある。是よりも三代後の善六(善兵衛の子)の書いたものの方が、要領を得ているから写して見る。
床島井堰所発端之次第申上覚
両郡畑田筋新溝御仕立之儀正徳二辰年より御取掛同年早田村分土居尻より縦堰を以水口御明ニ相成候処水乗兼御当惑之御模様と相聞追々御評議の上御郡御奉行安西次兵衛様 山田善兵衛様御境筋之儀ニ付夜々密々御見分御座候処筑前長田村と当御領早田村畑方双方共ニ永荒地に相成御境茂分明不成争論之場所ニ御座候此処より水口御明に相成候得者水乗茂至極宜少南ニ寄候而は砂地ニ而溝筋難保様子ニ付是非右場所より水口御仕明に不相成候而は往々溝筋難保存候水乗茂宜敷無御座候由御決断ニ相成其上両郡筋一流下之潤ニ茂相成至而御大切の御儀と奉存私曽祖父早田村庄屋善左衛門同村分ニ相違無御座旨一命を投打申出候ニ付同四午年右両村分論所より御掘掛ニ被遊候処筑前長田村より大勢罷出石礫打掛候ニ付当方より茂同敷石礫打掛相争居候内長田村百姓と名乗拾二三人草野又六様前江罷出此所長田村地方之所伺分之訳ニ而掘立有之候哉返答如何と差詰申候ニ付曽祖父善左衛門早速罷出御役人は何楚御存被成候儀無之素リ早田村分ニ相違無之候ニ付拙者共明申達候間掘立ニ相成申候御役人江決而麁抹(粗末)致間敷旨申候ニ付同人儀を直に召捕筑前方へ連越申候 夫より夜通御普請ニ而御掘溝出来通水ニ相成申候扨善左衛門儀三ヶ月余リ長田村ニ而番人大勢付居地方境之儀を色々吟味昼夜稠敷責候得共只今御掘川之儀は早田村ニ其紛無之段幾応ニ而茂速ニ返答致候ニ付後は可致様無御座善左衛門呼取呉候様塩足大庄屋元へ毎度掛合候得共一旦連越候人柄ニ付其元ニ而勝手次第被取計候様呼戻候儀不相成由返答有之候ニ付甚持扱候様子ニ而御井郡筋心易庄屋之内ニ相頼色々手を尽相談仕候ニ付御井郡筋庄屋之内より長田村江呼ニ参善左衛門儀御井郡之様ニ引取暫滞留其後宿元江罷帰申候 其筋同人義村方百姓中へ申聞候は長田村ニテ稠敷被責身体も難絶有之候得共此節極々太切之御儀ニ付少茂不苦彌早田村分ニ相違無之段一命ニ懸申答置候 以後いつれ茂左様相心得居候様委敷申聞置候由善左衛門儀長田村ニ而被責候節急所ニ被当一生病身ニ相成相果申候 尤同人儀連越候拾弐三人之者共長田村百姓とは名乗候得共実は百姓等ニ而無之撰人ニ而差出ニ相成候儀と其後相知申候
一、善右衛門長田村江連越留置候ニ付同人倅善六村方才判仕居候処右御仕明水口へ長田村より乱杭夥敷打出用水大ニ差至夫而巳不成親善左衛門一命を投出早田村分ニ相違無之明段長田村ニ而も申切返答致候趣内通仕候ニ付倅善六儀茂右乱杭為打出候而は御太切之御場所決而難相済其上親善左衛門勤切茂難相立存筑前方より如何体之儀仕掛候とも夫に不拘猟師之体に身をやつし夜々百姓召連銘々綱致持参打出候杭木全抜取申候 又々幾度茂打出申候得共幾度ニ而茂抜取候ニ付如何存候哉後は乱杭茂打出不申候
一、早田村運々儀以前者井堰御仕立之所に而御座候得共水行打変水難絶御座候故只今之場所江村置仕跡地之儀は畑方ニ開明土地合茂大体宜敷御座候処右井堰所御仕立ニ而全井堰下○(不明)地ニ相成申候 曽祖父善左衛門所持之地方三町余御座候然所右申上候通○(不明)地に相成申候得者家督相滅自然と追送り不勝相成申候
右之通両郡畠田新溝筋御仕立ニ付曽祖父善左衛門筑前領長田村へ被召補候一件申伝候始末様子申上候 以上
卯弐月 竹野郡早田村庄屋 善 六
(五)其後の堰所
此の増築によって恵利堰も愈々堅牢無比のものとなった。筑前からはしばしば破壊に来たので筑後では番人を置き、附近の村々へお触れを廻して万一に備えて居る。
丸林家の古記録によると
床島井堰筑前より引崩狼藉之仕形ニ付被仰渡左之通リ
一、竹野郡床島井堰先頃洪水之節大勢罷越堰所引崩狼藉之仕形有之候ニ付向後守方之儀別紙覚書ニ而申渡候間被得其意尚又委細被申付候 尤御郡方役中より茂申付候様申渡候 堰所番善右衛門より被相渡候鉄砲之儀者各より被請取可有御渡候玉薬等之儀申出下候はゝ早速御役所より可被仰渡旨吉田隼人 稲次縫殿別紙を以被仰渡候
一、竹野郡床嶋井堰之儀大切之場所柄ニ付御用無之者右続地河共入込之儀堅御停止被仰付置候 向御右堰所江蹈込狼藉之仕形有之節者勿論惣して御制禁之場所江狼藉に蹈込候者於有之者無遠慮打ひしぎ可申候
一、右堰所番人善右衛門鉄砲五挺玉薬ともニ今度被相渡候間狼藉之者有之候はゝ打放可申候
一、右堰所番弥心掛相守若不意之狼藉有之節者竹貝吹近村より駈付尤塩足大庄屋方より茂乞才判早速人夫可差出候 右堰所之儀平日は勿論洪水之節茂溝下組村より可相守事ニ候得共場所相隔果急之節は間に合かたく候間床嶋村其外手寄之村々より平日無油断心掛不意之義有之節者早速駈付候様兼而可乞覚悟候
一、洪水之節者番船人数等茂三拾人程差出置可然候 溝下之組村より者通路難成可有之候間塩足組手寄組より差出置追而可致立用候 洪水之節専一可心掛候右之趣堰所手寄村江申付置自分儀茂弥心用候様塩足大庄屋迄可被申聞候 尤溝下之組村場所相隔有之儀ニ者候得共別而大切ニ可心掛候
元文二巳年
となって居る。
堰を築く時筑前方は、十一ヶ村は水底に沈没すると云って故障を申立てたが、出来上がって見ると却って筑前領の吉末、倉園、白鳥の三村は水掛りが良くなった。 しかし筑前方は決して堰や溝の破壊を止めぬ。筑前方故障の真意は両国の境界線にあったらしい。そのまゝにして置くのは甚だ面白くないというので遂に天領豊後日田の年寄関村左平が仲に入り百方尽力の末、筑後早田村の一部分を筑前領古毛村の一部分と交換することになってやっと落着した。即早田村分一町八反三畝六歩を古毛村へ与え、古毛村の一町八反五畝七歩を早田村分とした。時は元文二年十一月二十七日で、是から彼我の感情も融和して以後恵利附近には些の波瀾も起らなかった。
(六)灌漑反別と水路
堰溝が出来上がって灌漑範囲は三十八ヶ村に及んだ。元文元年(完成後二十三年)北野大庄屋の実測によると、一千九百三十九町二反八畝十五歩となって居る。
現今では北野、大堰、大城、弓削、本郷、大刀洗、宮ノ陣、味坂、金島九ヶ町村、その面積は約三千町歩に及んで居る。水道の数二百八十四ヶ所、橋梁五百二十、水路の延長七万七千五百三十間(約百四十三km)となって居る。
(七)聖恩枯骨に及ぶ
大正五年の秋陸軍特別大演習が肥筑の野に行わせられ鳳輦を福岡県下へ進め給うに当り同十一月五日、六士に対し左の通り、其功績追賞の恩命を辱うした。まことに天恩枯骨に及ぶ、泉下の六士感涙に咽んで居る事であろう。
(各通) 故 草 野 又 六
故 高 山 六 右 衛 門
故 秋 山 新 左 衛 門
故 中 垣 清 右 衛 門
故 鹿 毛 陣 右 衛 門
故 丸 林 善 左 衛 門
特旨ヲ以テ位記ヲ贈ラル
大正五年十一月十五日
宮 内 省
(各通) 故 草 野 又 六
故 高 山 六 右 衛 門
故 秋 山 新 左 衛 門
故 中 垣 清 右 衛 門
故 鹿 毛 陣 右 衛 門
故 丸 林 善 左 衛 門
贈従五位
大正五年十一月十五日
宮内大臣従二位勲一等 男爵 波多野敬直宣
有難き極みである。
(八)大堰神社
此の堰渠の恩恵の浴して居る郡民は、功労者が其昔祈願を籠めた江戸水道上の水神社で、毎年祭典を営んで謝恩をして来たが、大正二年築堰二百年に相当したので、十一月堰の畔で大祭を執行し、大正三年功労者を神社に祭祀しようとしたが実現しなかった。大正十三年四月ニ十三日いよいよ起工式を挙げ、草野又六以下六士を祭神に加列し、大正十四年十一月二十九日を以て、鎮座大祭を執行した。三井郡大堰村の郷社大堰神社が即ち是である。