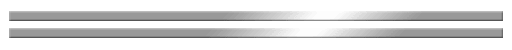
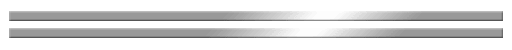
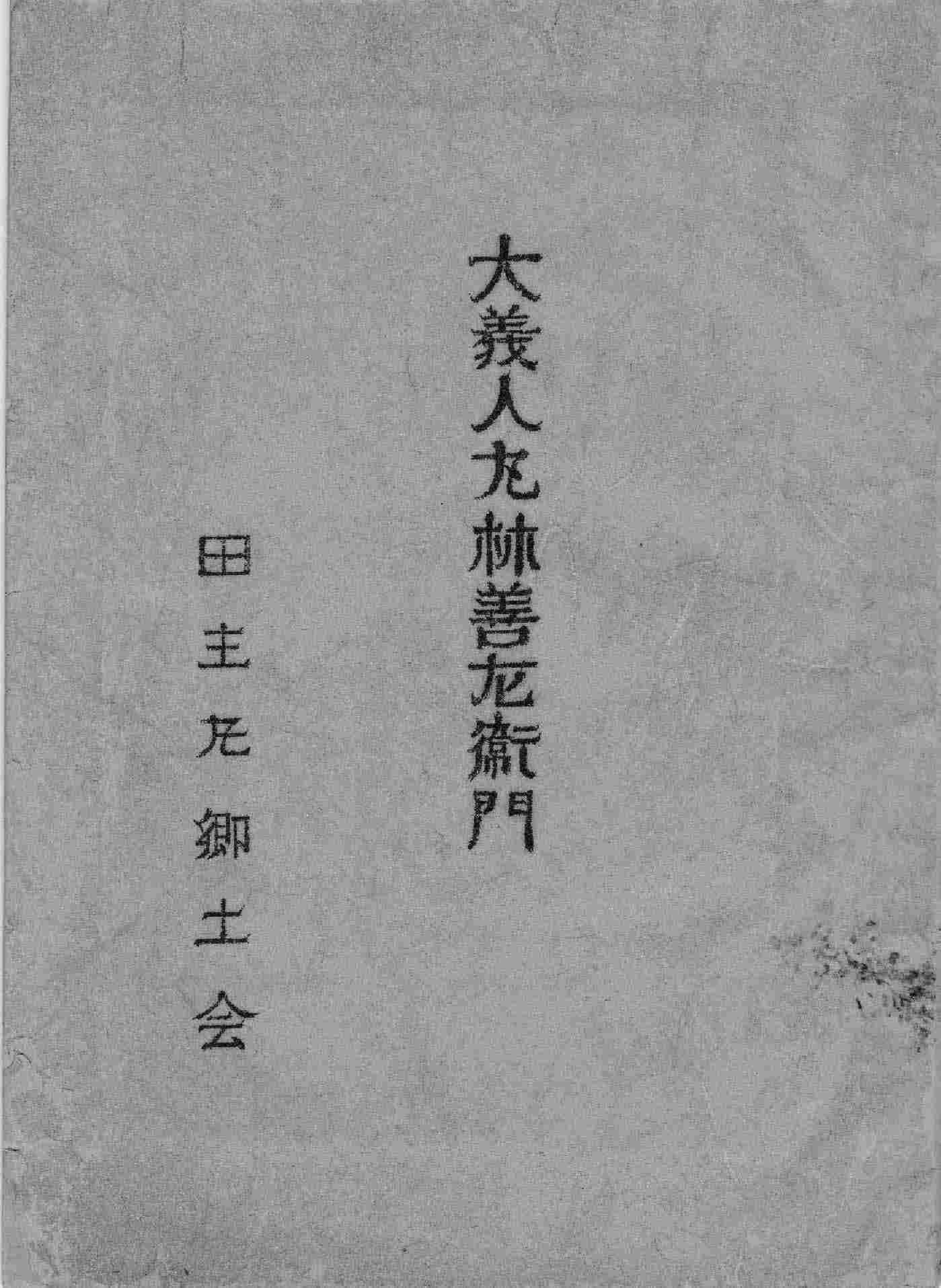
大義人丸林善左衛門
田主丸郷土会
第一章 恵利堰(床島堰)
この堰は今から二百二十四年前、中御門天皇の天徳二年(徳川家宣将軍時代)に築かれたものだ。
丸林家文書には次の様に記されて居る。
竹野郡床嶋堰所用水新溝出来覚
一、御井郡弐拾八ヶ村古田旱損地天水所多及難儀且又畑方水損所多為困窮候ニ付床島村東藪際早田村分水道仕立新溝被仰付被下候者新畑田出来古田旱損茂無之耕作取続申度段宝永八卯春依願溝筋見積書付持出重々御吟味之上竹野郡田主丸六郎左衛門と申者曲尺見申候処弥水乗宜畑田作七百町余出来入用銀目録他(或いは作?)五拾貫目余拝領人夫惣御郡ニ被仰付被下候様願出候
同秋正徳元卯十月十四日願之通被仰付入用材木拝領造用銀拾三貫五百目拝領被仰付翌辰二月廿一日ヨリ惣御郡夫を以御普請被仰付同五月迄大概御普請相仕過古田畑田並ニ根付仕候
但井堰百七十間恵利瀬形石組長百間
右件借銀享保十二未年より其年迄五ヶ年祇ニ而返納仕候
一、右堰所入用多溝下中年々及不申候ニ付江戸水道所より上床嶋堰所迄惣御郡役ニ被仰付候
一、右新溝口願場所下リ水乗不足ニ付床嶋村下筑後川筋堰立被仰付候
一、恵利瀬形船通在之候而者水乗悪敷候ニ付正徳四午年船通堰留旱田浜筑前境ニ川堀○(不明)床嶋村堰所之上只今之場所船通被仰付候(是は次の恵利瀬の増築に関するもの)
一、右堀鑿之場所筑前御領境少々流通石船往来筑前より相妨候ニ付恵利瀬古川筋築留〆只今之川筋ニ罷成早田浜全く当御領ニ相極リ候(之も(三)恵利瀬の増築に関するもの)
一、床嶋堰所恵利瀬形石組之儀享保九辰年より・・・・・(省く)
一、享保二十卯年七月・・・・(省く)
一、右用水引受候村数
御井郡
守部村 八重亀村 高嶋村
赤司村 山須村 稲数村 仁王丸村 塚嶋村
陣屋村 中村 今山村 十郎丸村 高良村 鳥巣村 石崎村
上弓削村 下川村 江戸村 染村 安永村
御原郡
今村 下高橋村
総而 弐拾八ヶ村 本願
御原郡
御井郡
古賀村 八丁嶋村 鷹取之須村 森村 五郎丸村
〆拾ヶ村 後願(此の分は不正確)
合参拾八ヶ村
一体筑後川の北岸の旧三井、三原二郡は土地は広くて地味も肥え其上川にも近いのに川面よりも高いので久しく荒れ地のままで所々に田地はあっても一に雨水を待つと云う状態であったから五穀は収穫少なく、不幸にして旱天年となれば居民は忽ち餓飢に迫られ四方に流離する者が多かった。それで各村とも年々疲弊するばかりであったが霊元天皇の寛文四年(徳川家綱将軍時代)彼の有名な五庄屋によって大石長野の堰が造られた。是にならって一大堰溝を開きたいとの意見は、此の地方各村庄屋にあったが浮羽郡大石よりも約五里の下流に当たり、川幅も広く、水勢は荒く其の上此の地は筑前黒田領と筑後有馬領との境であり下手な事をすれば一大紛擾に起す恐れがあるので、率先して工事に当ろうとする者もなく、延び延びになっていたが遂に鏡村庄屋六右衛門、八重亀村庄屋新左衛門等がけっ起した。中にも六右衛門は僅か三十歳に過ぎないが、最も胆略と知謀あって首唱者となったのである。
宝永七年の春またもや大旱魃で村民の流離するものが、甚だ多くなった。六右衛門は最早猶予すべきでない是非とも筑後川の水を引く工夫をせねばならぬと考えた。幸い久留米藩の目附遠山氏の隠居六郎左衛門の尽力によって、郡総裁本荘主計同市正父子を動かし、本荘父子の情によって、家老の内諾を得た。喜び勇んだ六右衛門は、高嶋村庄屋甚右衛門父子を訪うて、互に決死の覚悟で事に当る事を誓い、公儀向けの事は六右衛門、金銀物入の儀一切は甚右衛門と分担を定めた。
更に稲数村庄屋清右衛門等各村庄屋も加って、堰溝築開の願書の調製に着手した。時に宝永七年八月であった。其の願村は
御井郡(今三井郡)
守部村(現大堰村の中) 江戸村(大堰) 下川村(大堰) 八重亀村(現金島村の中)、
高嶋村(金島)、
稲数村(大城)、 仁王丸村(大城)、 塚島村(大城)、
高良村(弓削村の中)、 鳥巣村(弓削村)、 石崎村(弓削)、 上弓削村(弓削)
御原郡(現三井郡)、今村(現太刀洗村の中) 下高橋村(太刀洗)
計二十八ヶ村
しかしいざ願書提出という時になって、何故か上弓削、江戸、染、下川、安永、今、下高橋七ヶ村は之に加わらなかったので二十一ヶ村が連判した。六右衛門はこの願書を郡奉行、国友覚右衛門に提出したのは、宝永七年十月二十日であった。
今その設計の大要を見ると
一、筑後川を恵利瀬の所で堰き止め其一部に水余を造り、之を舟通しとすること。
二、堰の北岸から床島に向けて、一大溝を造り河水を之に導くこと。
三、床島に水門を設け其水門から吸取する水は、溝に流れて千二百余間下の江戸前に至り、此所から漸次派を分けて三十余村の田地を灌がいする。
四、新溝開通の暁には古田の灌漑は勿論、別に藪林、畠を開発して、七百余町歩の新田を得る見込みあること。
五、従来は上納米も不足勝ちであったが、この工事完成の上は、米大豆差引き一ヶ年、約七千俵の増米ある見込みであること。
六、築造費は、銀五十貫目を要すること。
七、此築造費五拾貫目は藩から借用して年賦で返済すること。
八、人夫は総て郡役にすること。
九、水道に入用の材木は手寄りの官山から拝領すること。
十、領内の石のみで不足する恐あるから他領から購入する。
十一、小石を運搬するため船二十五隻を要すること。
十二、岩並に割石は御井、山本両郡の内手寄りの山から拝領する。
十三、大工、木挽、杣取の前金銀其他諸品買入の為銀子十貫先ず借用すること。
等となっている。
時の藩主は梅巌公則維で英明、治道に精励せられて居たので、願書を一覧せられ、大いに之を壮とし便宜を与えよとの沙汰があった。
因って藩では工事監督として野村宗之丞、草野又六を遣はし、請うままに官林の伐採を許し、銀子も貸下げ、一挙にして工事に着手しようとした。
然るに此の事を伝聞した筑前領の諸村は驚いた。大川の中流を堰止め、恵利に水門を設けられては、其上流に臨んだ我が諸村は、洪水の際は残らず水底に沈むというので、川越六之丞と云う者十一ヶ村の庄屋の抗議書を持って、久留米藩に迫って来た。久留米藩も躊躇して工事も沙汰止となった。各庄屋の煩悶は想像に余ある。鏡村庄屋六右衛門は必死の運動を藩に続けたが、此の上は神仏の御助けによる外ないと、高良玉垂宮に七日の断食をして祈願をした。神もその心事を憐まれてか藩も大いに決する処あり。水道口を二十町程度引下げ、堤防も築かず一歩筑前に譲って置いて断呼として工事に着手した。時に正徳二年正月二十一日。
この時の請負奉行は野村宗之丞で、総取締が草野又六である。鏡村庄屋六右衛門は御用手伝、御用聞となり、稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門の二人は共に溝筋諸品裁判となり、高嶋村庄屋甚右衛門は金銀仕払預り役となっている。
外に十一ヶ村庄屋は各々任についた。
中にも草野又六は中心人物として、最も重きをなし工事の大部分は彼の力によるものとさえ云われて居る。彼は山本郡大橋村の鹿毛宗五郎の二男で、同郡草野村の草野五左衛門の養子となった。天性剛毅果断、胆力人に超え水利墾田の術に長じて居たので抜擢せられて下士となり、土を開き利を興した事、前後幾回なるを知らぬ。又親に仕えて至孝、智あり涙あるの士であった。
斯くて正徳二年正月廿一日から三千五百人宛の人夫を指揮し、堰所、溝筋共同時に工事に着手した。堰の長さは百七十間、筑後川でも、この辺は名に負う奔流急湍であるから、其の水を遮断すべく築成するには非常な困難であった。一体獺の瀬堰も大石の堰も、山田の堰も、恵利の堰も、非常な難工事である。それは一見すれば明らかである通り、第一どの川でも堰はそこで水準を不自然に一時高めて、川面より高い地へ水を導くのだから、最初から勾配のある所へ築かねばならぬ(平々坦々とした所へ築いても用をなさぬ)。従って急流へ築造することになるから難工事は始めから覚悟の前だが、筑後川は全国屈指の大川で、水量が多く、川幅は広い。さればこそ是等四堰は全国堰中の難工事と呼ばれているのだ。殊に恵利は最も下流であるから上流三堰に比して、水量も多く、川幅も広いので如何に苦心したかという事は素人の我々でも直観する。今日川下からこの大堰を見上げた時何ら文明の利器を有せぬ徳川中期、よくも人力のみで造ったものだと驚嘆の外はない。
如何に、大木、大石を投込んでも、木の葉のように推流されるので流石の又六も術の施し様もなく、失望のあまり家に帰って殆んど病人となった。処が其母は又余程賢夫人で又六を門前に呼び出して、仰いで水縄の連山を指して、彼を見よ、あれだけの土や石があるではないか、高の知れた筑後川、何の填まらぬ事があるか、と励ました。又六聞いて奮起し、石小石を数隻の古舟に積み船と共に沈めたので、やっと基礎を固める事が出来た。更に近くの山から数十万の大石を運んで来て、小石は別に俵に詰めて五十万俵を作ってそれを一時に沈めた。
それでやっと河水は堰かれて新溝に入った。しかし水門は筑前領の抗議によって当時の設計を変更して新溝口から約三十六町下の江戸前という所へ二個設けた。
かうして堰と溝とは大体三月中頃には出来上ったが、恵利堰は急ぎの工事で洩水が多く新溝に流れてくる水量が、予期したよりも少い。更に鏡村庄屋六右衛門の深慮と果断によって、筑前から流れて来る佐田川を一夜に新溝に引いた。それで水量は著しく増し藩も民も喜んだのである。
恵 利 堰 の 増 築
出来上がった恵利堰を見ると、船通しがあって堰の一部は開放せられて居るので、多量の筑後川の水はここから流れ去って新溝へは充分注がぬ。それで各村の用水は不足であるのに其上御原郡の平田、小島、上高橋、甲条、鵜木、古賀、八丁島、恋之坂、森、五郎丸の十ヶ村が配水を懇願して来たので、之を許すと合せて三十八ヶ村となり、水は益々不足する。それで藩は正徳四年堰の改築を企てた。この度の上奉行は田山善兵衛で、普請奉行は野村宗之丞で、総裁判は草野又六である。又六は先ず恵利堰の船通を閉塞して百余間の石堰を増築しようと計画した。所が其の中程に竹野郡(現浮羽郡)早田村分で中曽、吉原という所がある(現在は中洲といって島形をなし御井郡分となって居る)。此の地は筑前領下座郡長田村と接して、久しい間荒蕪地となって居て其の境界は殆ど不明であった。筑前長田村の民は又六の計画を聞いて之は一大事、もし恵利堰の船通を閉鎖されては河水は停滞して、長田村の土地は甚しく湿潤となり、耕作を害し、殊に洪水の時は多大の惨害を蒙るし、船で筑後川を上下する時の不便は大となり、また黙って居ては中曽吉原は明に筑後領となってしまう。以上の諸理由によって中洲は筑前領であると唱え、筑後の作業船の通路に乱杭を打込んで工事の妨害を始め、遂には石堤を突し出し水勢を激せしめ筑後早田村の沿岸に流潟して来た。よって筑後の諸庄屋は憤激する。又六は長田村の庄屋にそれを取除くやう申込んだが、問題は容易に解決せぬ。又六も頗る躊躇した。この時早田村の庄屋善左衛門が進み出て、此処は昔から早田村の分である。他人は何と云っても此の庄屋の自分が知って居る。遠慮は御無用、早く工事を開始するがよろしいと意気衝天の慨があった。この一言によって又六も励まされ、一日に人夫二千人宛も召集して一斉に手を下し、先ず船通しを新に中曽に開掘し船は筑後川から新川に入り、此の船通しを過ぎて再び筑後川へ出るやうにした。
恵利堰の船通しえは大木、巨石を積み沈めて堰止め、深く筑前領の岸陸に沿うて、新川と称する水路を通したので、筑後川の水は多く此の新川から溝に入り、水量は甚だ豊富となった。今行って見ると溝でなく川だ、しかも甚だ深くて恐ろしい位だ。
恵利の石堰は先年築いた分と合すと、長さ二百七十間、新川の捨石の所まで加えると、五百間近くもある。堅牢無比、人間の作ったものとは思われぬ。筑後川の一偉観である。
第二章 義人早田村庄屋善左衛門
此の工事中であった。筑前長田村から大勢の人足が来て、手当り次第に礫を投げるので、筑後の方も亦応戦して双方入り乱れて正に一大惨事を起こそうとした。その中筑前方から風彩の賤しからぬ者十余人、長田村の百姓と名乗って草野又六の前に出て、此所は筑前領である、何故に掘立つるかと詰問した。此の時筑後早田村の庄屋善左衛門が進み出て、それは役人方の知る処ではないから、役人方に対して粗暴な振舞あってはならぬ。又自分先祖の代から庄屋として何も彼も委しく知って居る。此所は早田村分に相違無い、と述べたので筑前方は更ば今少し相尋ねる次第があると云って善左衛門を長田へ連れて行かうとした。筑後の人夫はやらぬと抵抗する。しかし、善左衛門は制して、ともかくも行って理非を明にして来る。工事は中止するに及ばぬとて単身虎穴に飛び込んだ。彼は一命を棄てて先方に行って掛合い、筑前領の者の注意を一身に集め、その暇に恵利堰の工事を急がせようと考えたもので、真に犠牲的大勇猛心の極度を現したものだ。この精神こそ日本魂の真髄と云うべきである。
さて善左衛門を連れ去った十余名の者は長田村の百姓と云ったが、皆福岡藩士であったとの事で、善左衛門は三箇月余りも、番卒を附けられ大勢の者で境界の事を吟味して、昼夜厳しく責立てたが、彼は少しも屈する色なく前言を固持して、中曽吉原は筑後早田村なりと言明するばかりで、とうとう筑前の連中も持て余し、善左衛門を引取ってくれと筑前徳渕村大庄屋から、竹野郡塩足村大庄屋え申込んで来た。塩足村大庄屋は今が困らせ時と云うので、一旦連れて行った者であるから、お前の方で勝手に取扱ってくれと、はねつける。筑前方はいよいよ持て余す。其の虚に乗じて、昼夜兼行で工事を取り急いだので、恵利堰の増築は竣工した。
善左衛門は私かに御井郡稲数村の庄屋清右衛門に頼み、郡中の某家に引き取り暫く滞在して後村に帰ったが、筑前の拘留呵責に遭って身体の自由を失い、遂に病死した。身を殺して仁を成すというが、その壮烈義烈武士も遠く及ばぬではないか。非常に処する真の精神とは是ではなかろうか。只そればかりでは無い。彼は其の支配地三町歩を此の工事の為に失った。又畠地六町歩を、中曽吉原え新川を掘るために、荒地とされた。又床島の東に飛地のあったのも一町ばかり失った。そもそも早田村は筑後川の南にあって、竹野郡に属して居るのだ、北岸の御井郡に如何なる水道が出来ようとも何等の御かげを受けるのではない。彼こそ他郡公益のため、一身一家を犠牲にしたのである。是程美しい、是程尊ぶべき行為があろうか。武士道が徳川中期に至って、江戸町人気質となり、更に百姓気質となったと聞くが、我等はそれを遺憾なく善左衛門に於て見るのである。前に私が彼と、高山、秋山、中垣、鹿毛等の諸庄屋と少しく趣を異にして居ると云ったのは、こゝである。即ち四人の庄屋等は何れも皆己の村に水溝を掘るのであるから決死の働きをするのも或いは頷かれる点もあるが、善左衛門は自分の村とは無関係の他郡河北の為に身は死し、一家は田地を失い以後非常な困窮に陥ったのである。今日三井郡恵利堰灌漑九ヶ村は、彼を神と祭って居るのは当然中の当然で、その感謝は丸林家の子々孫々に及ぶべきであらう。
善左衛門の子の善六も亦父に劣らぬ義侠の士であった。宝暦二年早田村分の中曽の荒地に、櫨木の植付けを願ったが藩は大切な堰の所在地であるから、後で問題が起っては、と云うので之を許さなかった。藩の処置は甚だ徳に背いたものである。しかし善六は少しも怨まないのみならず、筑前領の者が、新川口に乱杭を打込み恵利水道に妨害を加えようとした時も、父の志を継いで身を猟師にやつし、夜中之を抜き取ること再三に及んで居る。此の親にして此の子あり。私は丸林父子の事跡を調べて限りなき尊敬と感謝と、愉快を覚えた。
注 以上第一章第二章は昭和十一年十二月発行 鈴木昇三氏著「義人丸林善左衛門と恵利堰」より転載
第三章 第一回丸林善左衛門顕彰追悼会を催すに際して
一 丸林善左衛門
久留米の大詩人宮崎来城は、明治四十三年八月福岡日日新聞に「鬼工録」を連載している。最後の十一回分に床島堰並びに丸林善左衛門の偉功を書いている。宮崎来城は「丸林善右衛門」としている。明治四十五年発行の「浮羽郡辞書」にも、大正四年発行の「浮羽郡案内」にも「丸林善右衛門」となっている。昭和二十七年発行の「宇規波」第一号にも「丸林善右衛門」となっている。
大正十四年十一月発行「大堰神社と床島堰」では、「丸林善左衛門」である。
昭和十一年十二月発行福岡県中学明善校 鈴木昇三氏「義人丸林善左衛門と恵利堰」では、丸林善左衛門である。
善右衛門がほんとうか、丸林善左衛門がほんとうであろうか。丸林家に残っている「竹野郡早田村庄屋先祖代々名附」によれば
第一代庄屋源四郎が慶長元申年より元和七年酉年迄 弐拾六箇年相勤申候より はじまり第六代が善左衛門である。
正徳元卯年より享保十三申年迄拾八ケ年相勤申候となっている。
ここに私共は義人丸林善左衛門は善右衛門でなく、善左衛門であることを、はっきりしなければならない。
二 恵利堰
恵利堰は普通床島堰と云われているが、昔は筑前をはばかって、称したものであるが、所在地は、床島でなく恵利だから、今は恵利堰と称することが適当である。床島の新川にも小さな同名の堰があるから、まぎれ易い。
恵利の対岸 中曽中原の堰は、早田庄屋の支配地で、筑前領長田に接していた。この長田との境、早田分に新溝を掘ったのである。
宮崎来城は「床島堰の大半は浮羽郡の柴刈村恵利に築成せられている。従って恵利堰と称するのが至当だけれど、当時、筑前と国際上の紛議を惹起するの恐れあるとし、床島堰と名づけたものであるそうな」と書いている。
第一期第二期の大工事は、恵利の瀬を堰き止めて成就されたのである。私共は床島堰と称するよりも、恵利堰と称する事が本当である事を知るべきである。
三 大石、長野堰工事との比較
大石長野堰は、寛文四年四月十一日に起工されている。今を距ること二百九十六年である。これから四十八年後の正徳二年正月二十一日に河堰工事、溝掘工事を同時に開始した事が、恵利堰である。今を去ること二百四十七年前である。大石長野堰灌漑反別は二千三百五十六町七反七畝二分であり恵利堰灌漑反別は、三千町歩である。
大石長野堰は、第一期、第二期、第三期、第四期工事が行われたが、第四期工事の竣工したのは寛文七年四月二十七日であるから起工から四年目である。その後、洪水毎に修繕をし、その後大石築瀬石堰を築造し恵利水道をひらいている。これ迄に二十四年を経過している。
筑後川の北岸旧御井、御原二郡は土地は広くして地味も肥え、その上筑後川に近いのに、土地が川面より高いので、久しく荒地のままで、所々に田地はあっても、ただいたずらに雨水にたよるばかりであった。大石、長野堰が五庄屋の努力によって完成したので、御井、御原郡民も一大堰溝を開きたいとの意見をもっていた。然し、この土地は筑前黒田領と筑後有馬領との境であるから、一大紛擾争が起る事が予想されるので、率先して工事に当ろうとする者がなく、のびのびになっていた。
大石、長野堰が起工されてから四十七年目の宝永七年旱ばつのため居民が、しきりに流転するのを慨き、断全水道の開さくを志したのが鏡村庄屋六右衛門、稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門、高島村庄屋甚右衛門等である。
恵利堰は正徳二年正月二十一日から着工し四月十三日に竣工している。八十日間で出来上がったのである。
正徳四年恵利堰増築工事が行われている。丸林善左衛門が真面目を発揮したのは、この時である。
恵利堰は大石堰より約五里の下流に位している。川幅も広く奔流急湍のため水勢荒く、この筑後川の水を遮断して堰を築成するには非常な困難であった。何等文明の利器を有しない、徳川中期、よくも人力のみで造ったものだと驚歎の外はない。
宮崎来城は「今其跡について文を見るに、規模の雄大なる、結構の堅牢なる、天造といわん歟、施設といわん歟、大石長野の水道に比して、或いは勝るとも劣りはせない。其の工事の困難なりしことも、亦推して知るべきではあるまい歟」と述べている。
恵利堰工事と大石・長野堰工事をくらべ考える時、恵利堰工事の方が難工事であった事を知るべきである。
四 民衆の力
大石長野堰も、恵利堰も、ともに百姓の力、民衆の力によって、成就されたのであるが、恵利堰の方が民衆の力のみで進められたといってよい。
大石長野堰は藩営で行われた。工事総指揮官普請奉行丹羽頼母は藩命を奉じて、国友彦太夫下奉行青沼市左衛門、下河仁左衛門、田中八郎左衛門、足立小兵衛、小頭古賀仁兵衛、中島忠左衛門、穴生権左衛門、同六太夫、軽率三十人を率いて来郡し、その監護の下に工事は進められた。
恵利堰の方は、普請奉行野村宗之丞、普請総裁判草野又六は事に当ったが、他の役割は庄屋十六人が受け持っている。久留米藩主有馬梅巌公は有司に命じて充分の便宜を与えはしたが、庄屋を中心として百姓たちが、やってのけたのであると考えられる。
大石、長野堰が藩営であり、宝暦十年三月有馬藩儒者入江修撰文の「大名石渠記」が額石に剛刻された。明治二年三月久徳重恭撰文の「長野水賽記」が水道口の額面に彫刻され、更に文政十年十一月には有馬藩儒官樺島石梁撰文の「三堰碑」が大石水道頭に建てられた。
長野水神社が創建せられたのは明治十五年十月十五日である。
草野又六、高山六右衛門、秋山新左衛門、中垣清右衛門、鹿毛甚右衛門、丸林善左衛門の六氏に対し宮内省より従五位を贈られたのは大正五年十一月十五日である。
大正三年築堰二百年に際し十一月堰の畔に於て大祭が執行された。大正三年床島堰顕彰会が組織された。大堰神社の鎮座大祭が執行されたのは大正十四年十一月二十九日である。
明治四十五年恵利堰上に巨大なる彰徳碑建設のことが企画されたが今日まで実現を見ないままになっている。
大石、長野堰の方は世に大いに宣伝された。これと比べると、恵利堰の方は官尊民卑の風潮の中で、顕彰のことが行われず、郷土人にもあまり知られていない。私共は丸林善左衛門を加えた恵利堰築堰の六偉人の偉業を大いに顕彰しなければならないと思う。
五 大義人丸林善左衛門
御井郡、御原郡両郡の百姓たちの願い……水がほしい……を願いとし、御井、御原両郡に沃野をつくって百姓の民生安定を、はかろうとゆう念願に燃えた丸林善左衛門であった。自分の村をよくしようとゆうのではない。対岸の百姓たちのために自己をなげうって進んだのである。
流れに沈んだ人柱ではないが、恵利堰を築堰の人柱となった丸林善左衛門こそは大義人と云わなければならない。
町村合併が出来ても、小さな部落校区のことばかり考えている傾向のある時、大義人丸林善左衛門の広大なる気宇を私共の模範としたいものである。
(昭和三十二年十二月十六日 第一回丸林善左衛門顕彰追弔会当日この小冊子を発行
田主丸郷土会長 福 島 政 太 )