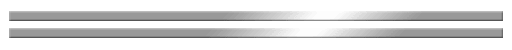
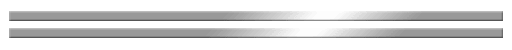
筑後川・床島堰渠水利史
1 堰渠設置の発端
2 堰渠工事の出願
3 工事
4 堰渠の維持管理
5 堰渠の構造と系統
6 堰渠の管理運営
7 恩賞の願書
床島堰渠が築造される以前のこの地域の開田状況はどのようであっただろうか。この地域というのは筑後川右岸地域で久留米市の宮之陣地区全域、小郡市の一部、北野町全域、大刀洗町の大部分である。旧藩時代は御原郡と御井郡に属していた地域である。
この地域の地形の現況は、筑後川本流恵利堰(標高14.15m)を起点として下流(西方)に向かい勾配約2,800分の1で右岸の扇状形に展開する起伏の少ない比較的平坦地である。僅かに中凹みの状態で筑後川畔では少々高い。畑地は鳥飼、西原、鳥巣、石崎、大杜、五郎丸、宮瀬など全て筑後川畔に集中している。
筑後川本流から直接取水していなかった時代では、支流から不十分な僅かの水を引くか、北方台地に点在する幾つかの溜池による灌漑で、相当の水田耕作がなされていたようである。もっともこの堰渠の築造年代である正徳2年(1712年)当時は既に65年前、支流宝満川に稲吉堰が設置されて流域約700町歩の水田灌漑がなされていた。
さて、この地域は筑後川の右岸(北側)にあって広大なる田園の遥か北方に宝満山があり、それから東は古処山を経て更に東方に延びる山並があり、そこから源を発する幾筋かの支流が本流筑後川へ向かってほぼ並行して流れている。下流から挙げれば、宝満川(古くは得川と呼んでいた)、大刀洗川、陣屋川、小石原川である。宝満川は小郡市の東寄りを北から南へ流れ、末は久留米市小森野を経て篠山城付近で本川に注ぐ支川で、現在小郡市内だけでも津古堰(かんがい面積約179町歩)、大板井堰(約155町歩)、稲吉堰(約735町歩)、端間堰(約200町歩)の四堰がある。大刀洗川はこの地域のほぼ中央を北から南へ、少し西へ向きを変えて流れ、宮之陣三条附近で本川に注ぐが、本来この川は排水河川で灌漑用には余り利用されていないようである。陣屋川も現在では全くの排水溝である。小石原川は古処山や江川ダムから発して甘木市と下流は三井郡大刀洗町を北から南へ貫流し、床島用水の江戸水道附近を通って北野町金島地区で本川へ注ぐ。合流地点の対岸は片之瀬になる。この川は各所に小規模の堰を設けて取水し、灌漑に利用している。この地区には、大刀洗町の本郷地区及び北野町の大城、金島地区の約500町歩を古くから灌漑していた松木用水というのがあったらしい。「床島堰渠誌料」その他の古い資料に記録がある。この用水は水量が乏しくて、少し照りが続けばすぐに枯渇したということである。床島堰渠が設置されて後享保12年春、この用水は廃止されていて、現在ではこの地方住民も殆ど知らない。松木用水は床島用水の設置よりもずっと以前から存在していたことは確かであるが、設置年代は明かでない。受益地域は平田、小島、上高島、江戸、下川、梁、安永、牛川、守部、八重亀、乙丸、稲数、赤司、山須等の14ヶ村で499町8反4畝分を灌漑していた、と記されている。現在の大刀洗の一部と北野町の相当部分である。ところで、この松木用水は何年頃設置されたか、そして取入口はどこであったかは明らかでない。
まず、設置年代であるが、受益地の内稲数、乙丸、赤司、山須等の旧大城村域内は筑後地方ではもっとも古くから発達した村落で、相当強大な勢力を持った豪族の居城があったところであり、田地の開田が早くからなされていたであろうことは想像できる。草野文書によると、永正5年(1508年)当時既にこの地方では約200町歩の知行分があったという記録がある。この200町歩の内には畑はもちろん水田もかなりあったと思われるので、その水源がおそらく、この松木用水であったであろうと推測できる。豪族がその権力によって遠く小石原川を遡り、筑前との国境付近に堰を設けて取入れたのがこの松木用水ではないかと推測される。また、この松木用水は大刀洗町本郷地区を貫流していたことは記録によって分かり、床島堰渠竣工事蹟によると“松之木井手(本郷川通り)”と書いてある。また、明治38年6月6日付けの「本郷村外一ケ村組合規約」によると、その受益田は春日10町5反3畝、甲条10町5反、上高橋12町4反、計33町4反3畝である。ところが安政6年(1859年)3月開設した4ケ村用水(床島用水の枝溝で現在は三ケ村用水と名称は変わっているが存在している。取入口は大堰陣社裏の遊水池の北東の角である)の受益田が同じ地区で面積も33町4反3畝と全く一致している。
以上、各種資料から総合すると、古くから松木用水が唯一の水源であって北は本郷地区、南は金島、大城地区を灌漑していたが、床島用水の設置によって南部地区は江戸水道の南水道にその水源を切換え、前記3ケ部落のみが松木用水掛かりとして残っていたところ、元来、松木用水は水量少なく不足勝ちでもあったので安政6年床島用水に水源を切り換え、水路は松木用水をそのまま使ったもののようである。ところで松木用水の取入口はどこであったのかという問題が残る。元禄14年3月有馬藩によって作製された地図があるが、その地図に江戸部落(江戸水道のあるところ)の北隣下川部落の更に北隣に小石原川に沿って「松木」という村名が明記されている。現在では、大刀洗役場において調査しても小字名としても存在しない。しかし、古図に記入してあるので、古くは存在していたであろう。現在の大刀洗町本郷地区に「井堰」という名称の小部落が小石原川の右岸に沿ってあり、そこに現在本郷堰という堰があるが、その堰のすぐ上流は筑前領である。土地の古老によるとこの堰の附近に松之木橋という橋が古い時代にあったということなので、現在の本郷堰が古記録にある松木堰であろうと、推測するものである。
1 堰渠設置の発端
床島堰渠設置前のこの地域における社会的状況は前述の左岸地域の場合と大同小異であったと思われる。すなわち水量豊富な筑後川がすぐ傍を流れ、且つ広大な沃土が広がっていながら取水することができなかったために、水田は極く狭小で、大部分の土地は荒地かまたは大豆、粟、稗しか栽培できない畑で、干ばつともなれば収穫もなく百姓は疲弊しきって、村を去る者もあって、いわゆる「亡所」となる村が続出していたようである。
ところで広い沃土があり、且つ水量豊かな筑後川が近くを流れ、しかもこの両者を統合すれば広大な沃田を開くことができることも充分分かりきっており、そしてそれに成功した先例が近接の上流地域の山田堰、大石堰、袋野堰と3例もあるにも関わらず、何故に半世紀に近い歳月を無為に過したのであろうか。思うに次のような事情のようである。御井・御原郡一帯に引水するためには地形の関係から現在の恵利堰附近がぎりぎりの下限と考えられる。それより下流地点に堰を設けても水乗りせず、従って、少なくとも恵利瀬か、またはその上流に堰を設置し取水溝を掘る必要があった。ところで恵利瀬より上流右岸は筑前領になり、他藩領内に堰と溝渠を設けることはまず不可能である。もう一つの難点は、恵利堰、床島堰、佐田堰及びこの3堰を結び、且つ江戸前まで延びる幅広い水路(約4,000m)の通過地は床島村、鳥飼村であり、この2ヶ村は高食村と共に右岸にありながら竹野郡に所属していた。従って、他郡である御井郡、御原郡の村々灌漑のための堰の設置や水路掘りによって相当広い水路敷面積が費地になる。このことについて地元村たる床島、鳥飼村住民が真っ向から反対するのは当然のことであり、その解決は庄屋、大庄屋段階の交渉では到底不可能だと考えられていた等のことから堰渠設置の誓願も長い間躊躇されていたもようである。
ところが宝永7年寅5月24日付けで、惣奉行本庄百助(後に主計と改名)、本庄加兵衛(後に市正と改名)の名をもって次のような回状が出された。
回 状
一、畑田之事
一、野開之事
一、山開之事
一、山中猪寄其外植立之事
一、藪開之事
右之品々存寄望之者有之候ハバ不依軽重他領他村之儀タリ共無遠慮可願出候譬近郷近村之障リニ成候共可申出候其段遂吟味可申付候是又御僉議次第ニ可被仰付此段御家老中被仰聞候以下
寅五月二十四日
本庄百助
本庄加兵衛
この回状の意味は「右の開田に関する各項目について希望の者がれば軽重によらず又他領、他村に関係ある場合でも遠慮なく願い出でよ、たとえ近郷近村へ差し障りがある場合でも申し出でよ、その場合は重々検討して決定する、右は御家老様方の御意向である」と。
こうした異例の回状が出されるためには、あらかじめ裏工作がなされている。すなわち、鏡村御給人遠山六郎右衛門は70歳になるなかなか気骨のある人で、郡奉行本庄加兵衛と親しい間柄であるので、この方面から内々に工作をして遂に家老の了解を得て前掲の回状を出すことになったのである。この回状がでたことによって開田に対する藩の積極的態度がまず打ち出され、それに乗じて誓願したのであるから他郡、他村は少しの反対もできなかったのである。
藩庁に裏工作してまでも開田を促す回状を出させる程の熱意を鏡村庄屋六右衛門が持つようになったのには一つの物語がある。六右衛門はかねてから新田開墾の志をもっていたが、ある年伊勢参宮の途中大阪の川口において米や酒樽等が多くの船に満載してあるのをみて、新田開墾の気持ちを駆り立てられて帰った。その後ある夜夢の中で神のお告げがあり、“ふじの根や三葉四葉の富草・・・・・”という言葉があったというので、この不思議な夢のことを北野村大庄屋善左衛門に話したところ、善左衛門は、これは連歌の言葉であって富草とは稲のことであって新田成就、子孫繁栄の吉兆であるといって新田開田を大いに勧めたということである。宝永7年は干ばつのために百姓が村を離れるのを見ていよいよ意を決し、藩役人へ働きかけるのである。
2 堰渠工事の出願
鏡村庄屋六右衛門がこの回状を見たのは病気中であったが喜びのあまり飛び起きて直ちに高島村庄屋甚エ門、同與三右エ門の父子を其の自宅に訪れて、この回状の出た事によってかねて切望していた水道開削が公然と出願実施できることを告げ両名の決意を促して賛成を得た。しかし、この工事は並大抵の事では成功覚束なく、共どもに励し合って固く約束し、六右衛門は藩庁に対する交渉の任に当り、甚右衛門は経費、資材等の経理面を担当することを決めて、早速計画書、絵図面等の出願書類の作成に取り掛かった。宝永7年(1760年)6月18日晴天に乗じて八重亀村庄屋新左衛門、大城村長百姓長右衛門、高島村庄屋甚右衛門、同村長百姓喜兵衛手代又左衛門、山本郡蜷川村百姓夘左衛門等のいずれも開墾に堪能な者達の協力を得てナンバン曲尺を作り、川船に乗って本流を遡り竹野郡早田村川岸の対岸である筑前領との境目に古い荒籠の壊れ残ったのがある所附近に曲尺を立て、六右衛門と又左衛門が水中に入って測量しながら流れを下っていった。その結果鏡村東川表堤の内“クワンジ”という畑附近までの高低差が1丈6尺5寸(約5m)あることが分かった。一同大変喜んで直ちに、この事を郡総裁本庄市正に報告したところ、本庄市正は速やかに請願書を提出するように促したということである。郡方からも速やかに請願書を提出するようにとの催促が北野大庄屋善左衛門宛に出されている。そこで鏡村庄屋六右衛門は早速出向いて郡奉行沖長長兵衛、国友覚左衛門と会い測量の結果を詳しく説明したところ、両奉行も殊の外喜んで、これまた一刻も早く計画書や願書等を提出するよう促している。一方具体的に用水の取入口を何処に設け、その水路は何処を通して、水門は何処の地点に設けるかについては、その道の名人である竹野郡田主丸溝回りの六郎左衛門、八重亀村の大工甚左衛門を雇い、鏡村庄屋六右衛門、その弟興左衛門、高島村庄屋甚右衛門手代又左衛門、赤司村又三郎、その他各村の庄屋が立ち会って測量し。床島村の上流古刎のある附近に溝口を設け、それから水路を鳥飼を経て江戸前へ通し、水門は床島村に設ければ充分水乗りする事の確信を得た。そこで、いよいよ最終的な誓願書類の作成に着手した。これが宝永7年8月のことである。
そのときの願村は次の村々である。
御井郡では守部村、八重亀村、高島村、鏡村、大城村、乙吉村、赤司村、山須村、稲数村、仁王丸村、塚島村、中島村、千代島村、陣屋村、中村、今山村、十郎丸村、高良村、鳥巣村、石崎村、上弓削村、染村、下川村、安永村であり、御原郡では今村、下高橋村の計28ヶ村である。上記の村は現在の北野町のほとんど全域と大刀洗町の一部である。昼夜兼行で絵図、設計書並びに誓願書等の作成を終わり、まさに提出しようとしたその日になってなぜか上弓削、江戸、染、下川、安永、今、下高橋の7ケ村は願村からの脱退を申し出たので致し方なく残り21ケ村の連判で宝永7年寅8月21日に一切の書類を藩庁へ提出する準備は完了した。
ところがここに筑前側から抗議の横槍が入った。すなわち郡方奉行川越六之丞の奥書した藩境11ヶ村連判の書状により、この計画の中止を申し入れて来たのである。その理由は境界の問題もあるが、たとえ筑後領内であっても筑後川を堰き止めて水路を設け床島に水門を造れば、一度、洪水になった時には筑後川沿岸の筑前領村々は水底に沈むことになる、ということと、附近一帯の筑前領は湿田となり麦作は全く出来なくなるというのである。筑前側からのこの抗議によって久留米藩庁も工事の実施を決しかねて延期することになった。しかし、六右衛門等はいずれ近く解決して工事実施の運びとなるものと予測し石材、材木その他の資材、人夫、賃金等の準備に遺漏ないよう検討し、大要次のような誓願書を宝永7年寅10月18日の日付けで20日に藩庁へ提出した。「乍恐御内意申上覚」等によってその計画の概要を示せば次のようである。
(1) 筑後川を恵利瀬の処で堰き止めて、堰の北の端に溝口を設け、床島に向けて幅広い溝渠を造り河水を導入する。
(2) 床島に水門を設け、其水門を潜った水は更に延びる溝渠を西へ約1,200間(約2,200m)流下して江戸前で分派して未端各村々へ灌漑する。(水門設置の場所は後に変更される。)
(3) 堰渠工事完成すれば古田約800町歩の灌漑と更に約700町歩の新田が見込まれるが、これにも充分灌漑できる。(現在畑を水田にすることを願出ている畝数が約800町歩あるけれども、高地で到底見込みのない畑もあるので約700町歩と予測される。)
(4) 従来は上納米も不足勝ちであったが工事竣工の暁には米、大豆差引年に約7,000俵の増米が見込まれる。
(5)経費は銀約50貫目を要するが、これは藩から頂戴したいが、若し頂戴出来なければ拝借して5ケ年の年賦償還にして貰いたい。
(6)人夫は凡80,000人を要するので総郡夫にして貰いたい。
(7)工事に要する材木は松5寸角、6寸角、長さ2間1尺もの5,263本。楠板長さ2間1尺、巾1尺、厚さ2寸もの1,065枚、6尺杭木2,970本、竹860束を近くの御立山(官山)より無代で払下げ願いたい。(これについては、椎夫、賃金まで予約して何時でも作業開始できるよう準備を進めていたことが記録からわかる。)
(8)大工小屋3間に10間のものを3軒建てなければならないので場所を決定して貰いたい、又人夫小屋もおいおい建てなければならないので、その際はその都度お伺いする。
(9)領内の大工では不足して工事が遅れるので他領の大工を雇入れること。
(10)石材運搬船(石船)25隻を要するが内8隻は御井、御原両郡にあるので残り17隻を準備すること。
(11)山石や割石は山本郡内の便宜の山から無償採掘の許可を願いたい。
(12)大工、木挽、椎夫等の前賃金、その他諸経費が入用なので、さしあたって銀10貫目を前借りすること。
以上のような内容を盛り込んだ願書、見積書等を六右衛門が持参して郡奉行国友覚右衛門、沖長兵衛へ提出したのが10月20日である。
両奉行は非常に機嫌が良くて、今夜は泊まって明21日の結果を待って行ったらどうかと勧められていたところ、その暮れ方に筑前藩からの使者が、工事中止の抗議を申し入れて来た。六右衛門は翌21日朝早く両奉行のお伴をして本庄百助に会い、工事敢行を進言したが、藩では結局当分の間中止ということになった。その後筑前との交渉は書状のやり取りのみで到底埒があきそうもないので、稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門、高良村理左衛門の3人は大城村長百姓長右衛門、高島村手代又左衛門を同道して筑前徳渕の大庄屋空閑弥左衛門方へ行き、筑前の村々へ被害を及ぼすようなことはないことを力説したが、了解してもらえなかった。
こんな状況で翌正徳元年卯(1711年)も堰渠工事は中止になったままで、六右衛門は残念に絶えず久留米に行っては目付役太田市之丞と再三にわたって相談した。その際ある日、太田市之丞の勧めで高良神社において断食祈願することを決意し、12月8日夜亥の刻(10時頃)から7日間の断食祈願に入り15日朝己上刻満願し、粥をすすって帰った。翌正徳2年(辰)正月、六右衛門は草野又六へ書状を送り、堰渠工事の件はどうなったかを尋ねたところ、各方面とも情勢は好転して近日中には御許可になる模様で、又六も精々努力するつもりだと返事が来た。稲数村庄屋清右衛門へも正月18日同様の手紙が来ている。一方筑前側からの抗議の件については、なかなか話し合いがつかないので、一歩譲って次のように設計変更することになった。すなわち、当初の設計では水門は床島へ設けることになっていたが約20町(約2,200m)ばかり溝下の江戸前に水門、水道を設けることにし、溝の両岸には堤防を築かないことに変更し、このことを稲数村庄屋清右衛門等をして筑前徳渕大庄屋空閑弥左衛門宅へ至り通告せしめた。そして、その諾否のいかんに関わらず断固着工することになった。
正徳2年正月21日(1712年)、草野又六は床島村大川口の現地に藩内惣郡の大庄屋、庄屋を集めていよいよ工事開始するに当たり、人夫の割前や宿割等を決めた。その日次の工事役人が任命された。
一 新畑田御普請奉行 野村宗之丞
一 同 総才判 草野又六
一 御用手伝御用聞
守部村庄屋 善太郎
一 溝筋諸品裁判 稲数村庄屋 清右衛門
八重亀村庄屋 新左衛門
大城村長百姓 長右衛門
一 金銀仕沸預り役 高島村庄屋 甚右衛門
同甚右衛門倅 興三右衛門
一 書付絵図 大城村庄屋 三左衛門
一 水道大工山方 赤司村庄屋 吉右衛門
陣屋村庄屋 喜兵衛
一 会所諸受拂 千代島村庄屋 市右衛門
石崎村庄屋 彦右衛門
一 鍛冶山方 鳥巣村庄屋 三郎左衛門
十郎丸村庄屋 庄左衛門
塚島村庄屋代 惣助
さて起工は何日であったかについて、数日の違いであるが二説がある。正徳2年正月21日説と正月23日説である。「堰のながれ」(大正2年10月発行)によると「正徳2年正月21日ヨリ河堰工事溝掘工事等皆同時ニ開始セリ」とある。この説の根拠は恐らく「竹野郡床島堰所用水引請候溝出来之儀委細書上候様被仰付候ニ付申上覚書」の次の記録だと思われる。「・・・・・翌辰正月21日ヨリ惣郡夫ヲ以御普請被仰付同5月?大渠御普請相仕廻古田畑ケ田共根付仕候」、この覚書は後年元文2年9月の記録であって工事後25年経過して書いたものである。ところが工事について、始めから終りまで中心人物であった
3 工 事
このようにして筑前側との未解決の問題を残したまま、正徳2年正月23日に堰の築造と溝掘工事を同時に開始した。1日3,500人の人夫である。有馬藩には大庄屋が25組あったので1組140人で3,500人になる。草野又六は善右衛門宅に、鏡村庄屋六右衛門と守部村庄屋善太郎は半左衛門宅に泊まり、毎日朝早くから現場にでて3,500人の人夫を指揮し、堰を築造する者、溝掘りをする者等各持場で働く百姓たちを激励しながら1日6・7回ずつ見回った。溝掘り工事は大体予定通りに着々と進捗したけれども、堰の設置工事は非常なる難工事で、杭を打ったり、巨石や栗石俵を投じたりしてもたちまちにして押し流されて何の効果もないので、流石の又六も施す術もなく、失望落胆し、山本郡蜷川村の実家へ帰って一室に閉じこもってしまった。その時女丈夫の実母は失意の又六を門前に呼び出して耳納山を差し“又六あの耳納山があるではないか”と言って励ましたという話もある。そこで又六は最後には、数隻の古船に石を積んで船もろともに河へ沈めて基礎をつくり、栗石俵50万俵という莫大な石を投じてようやく不完全ながらも堰らしいものが出来たのである。
堰工事には50万俵の俵に栗石を入れて川底に沈めたりしている。わけても2月末日は国老有馬壹岐の見分があって、丁度3,500人の役夫が八幡川原(片之瀬と柳瀬の中間部落)から恵利瀬まで栗石籠を1人々々が持って1列に進んでいく光景を見た国老は前代未聞の見物であると誉めて帰った、ということである。
こうした努力の結果、堰も一応できあがり新溝への水乗りも良いようだから、草野又六は3月上旬から溝下末端へもそろそろ掘り進めることとして、人夫を手分けして各溝下村々への溝掘作業を始めさせた。ところが何処に欠陥があるのか分からないが、予想以上に水漏れが多く新溝への水乗りが不充分であった。丁度そのころ、本庄主計が見分に来て3月20日の夜塩足の宇兵衛宅に泊まり、関係役人全員を呼び寄せて言うには“予想外に新溝への水乗りが悪いがどうしたものだろうか、少なくとも鏡村や高島村の水田あたりまでは水が届くようには出来ないものだろうか”と。居並ぶ者は皆策もないので言葉なく、仕方なく夜更けて大雨の中を沈痛な気持ちでそれぞれ帰った。その夜又六は高島村庄屋甚右衛門宅へ泊まった。六右衛門はそれから1km足らず先の鏡村の自宅へ帰る途中、対策を話し合うため途中甚右衛門宅へ立寄り、明け方まで3人で話し合い、疲れて隣室で横になったが眠れず思案中に一案を思い付き、直ちに又六に言うには“私に考えがあるので井上組から出ている人夫106人と、集っている杭木と明俵(空俵)とを私に下されが明朝までには必ず水乗りをよくします”と、又六はこれを許す。3月21日夜六右衛門は床島村へ出かけ、井上組の人夫を集めて事情を説明し、“君等を見込んで選び、この大切な工事をするのであるから大いに精を出して働くよう”に命じ、またよく働いた者には明日休暇を与え、怠けた者は上司より厳罰に処せられる筈だ”と申し、直ちに佐田川に出かけ作業に取り掛った。作業は佐田川を河口から上流60間(約109m)にわたってその西岸側に幅1間(約1.8m)の溝を掘り通し、河口には杭を打ち小石俵を踏み込んで堰き止め佐田川の水をたたえて新溝へ引き入れるのである。
さて、本庄主計は宿所の塩足村宇兵衛宅を発し又六始め諸役人を連れて現場に来り、六右衛門に向かって直々に「大出来、大出来」と誉め言葉をかけ、あらかじめ用意されていた船に乗り、六右衛門自ら漕いで新溝を鳥飼村まで下った。
同じ年の3月31日水門の設置地点について悶着が起った。水門は最初は床島に設けるよう計画されていたが筑前側からの抗議等があって床島の西方下流江戸前に変更されていたところ、作業直前になって溝
翌4月1日主計は役人その他庄屋一同を江戸前に集めた。北側に諸役人と庄屋衆が全部居並び、南側には又六と六右衛門の2人が並んで向かい合っている。この時主計は、まず最初に“水門の位置は極めて重要であるから両方から私情を離れて充分意見を出し合うように”と言った。そこで又六は“この水門を金操池の方へ引き下げたら将来永らく上郷(高島方面を上郷と云い北野方面を下郷という)を灌漑することはできないから、予定の江戸前へ設置すべきである”と主張した。ところが変更を主張する側の大工頭宇部次兵衛(測量担当者)が申すには“測量を誤っていたので水門を下げなければ水は流れない”と主張した。その時六右衛門が“測量は誤っていようとも水は、もう水道口まで来ているではないか、今このまま予定通り江戸前に水道、水門を設ければ必ず水の流れは順調である”と強い口調で主張した。又六もまたうなずき、相手側は誰一人として一言も云う者はなかった。最後は本庄主計の判断で又六等両名の申分とおりに決定した。早速翌4月2日より昼夜兼行で江戸前の水道、水門の設置作業が行われ、数日で竣工した。ところが水道の地点が少し高目に又水乗りも悪いように見えるので又六は自分の主張が誤っていたのではないかという強い心配が出て来た。一方、六右衛門も心配でしばらく目を閉じ、心で高良山玉垂宮に祈って目を開けば、水はさらさらと水道の内に流れ入っていたのである。六右衛門は、これ一重に有り難き神助によるものと感涙した。大石長野堰渠の場合も新溝に初めて通水したときは極めて水乗りが悪く、関係者は非常に心配したものであるが、これは漏水と吸込みのためで、いつの場合も必ずある現象のようである。
かくして江戸前水道が出来上がったのは正徳2年辰4月3日か4日である。旧暦の4月中旬ともなればこの地方では、もうそろそろ苗代の頃で灌漑の水の必要な時期である。従って、江戸水道工事の頃は、末端村々へ至る枝溝掘り作業はもう既に完成に近くなっていたものと想像される。ところが4日5日に床島川口堰に漏水があり、心配なので非常召集のうえ、現場に詰め切って修理にあたったので7〜8日で修理完了した。このとき又六が言うには、“皆々精魂込めて本当によく働いてくれた。お陰で無事完成して末端の新田まで水も充分回るだろう、御苦労であった。どうか久し振りに我が家へ帰ってゆっくり休養してくれ”と。思えば、去る正月21日から4月中旬まで日数およそ85日間の我が家にも帰らず現場に詰め切って働き、漸く新畑田が出来て万民安堵いたしたのである。
いよいよ「床島井堰出来発端書留」も終わりに近付いたのであるが、ここでこの覚書について少々照会しておこう。この覚書は鏡村庄屋高山六右衛門が床島堰渠竣功の翌年正徳3年巳9月21日の日付で書き上げたものである。六右衛門は床島堰建設の中心人物であるので、最もよく本事業の発端から竣功まで詳細にわたって、知悉している者の一人であった。その彼が病を得て倅に庄屋職を譲り、隠居の身で後世のために記録を残したのがこれである。1年前までの生生しい記憶の覚書であるので最も正確だといえるであろう。恐らく本堰関係の資料の原典となるものであろう。後世にでた多くの資料は大部分がこの覚書を根拠にしているようである。
さて、この覚書の終わりのころの記録については触れておこう。3件書かれているが、まず、堰渠建設に功績があった6人の主だった人達を本庄主計父子が自宅に呼び、御馳走をして慰労かたがた感謝の意を表したこと、次いで竣功後安堵して張り詰めた気がゆるんで病気になり、庄屋職を倅に譲り、死を見つめるような感傷を述べており、最後に恩賞辞退の件を簡単に書いている。
次に病気の件について、彼はこう述べている。正月21日から4月15日まで約85日間家へも帰らず現場に詰切りで精根つくして勤め、ようやく竣功し新田も出来て万民安堵した。その後自分も気がゆるんで病気にかかり、堰渠工事の概要を後世の人の為に覚書して残しておくのである、と。その裏には、自分は病気になり何時死ぬか分からない今、ここで自分が記録を残しておかなければ年の経過とともに忘れ去られてしまうだろうという淋しさと責任感が伺える。
続いて六右衛門は次のような記録も残している。すなわち、堰渠竣功の年は7月14、5日頃には田植えも終り、水廻りも大体よかったので新畑田も豊作で、反当6〜7俵の籾がとれ、米の質も良好であった。それでも大変急いで工事がなされたため、不備な点もあって漏水が多く、末端の村々からは少々水不足の声があった。そこで翌正徳3年己春又々総郡夫を命じて堰の補修工事がなされた。ところが堰の切れ目から石材運搬船が流されて沈没し、大城村の喜一郎と鏡村の九市郎の二人が溺死した。死骸を探したがようやく3日後に発見されて悲しみの中に葬儀があった。その際、人の死に接した病身の彼の心境が伺える。溺死した2人の葬儀の際自分の心に浮かんだのは、大事業をなせばその成就の後、今までの緊張が緩んで、えてして病気になるということであるが、自分も恐らくそれであろう。とも角もこの様に病気になっては庄屋役も勤まらないので遠山氏に勤めに出している次男の與右衛門を呼返して庄屋役の名代を勤めさせている、というのである。
最後に六右衛門は恩賞辞退の件を簡単に述べている。正徳3年の秋、普請奉行野村宗之丞を訪ねたところ、自分等について惣郡奉行本庄市正から床島堰渠設置の功績により恩賞申請がでていることを聞いた。また、別に草野又六からも恩賞申請の内意を聞いたけれども御断り申し上げた。新田が出来たのは神佛の御加護と御上の御威徳及び時勢その他本庄主計様始め御役人方の御努力の賜物であると申し上げて置いた。
前述の大石長野堰渠の場合は五庄屋に対して毎年引高各200石宛を給するという命が出て、五庄屋はこれを辞退したが結局一回だけ受けた。床島堰の場合は、藩の命令はまだ出していないので一部申請が出た段階で終っている。自分等の功績を誇らず、病を得て寂しさを感じながらも“やるだけはやった”という大事成就後の大安心の姿であろう。
4 堰渠の維持管理
さて、正徳2年春、恵利、床島、佐田の3堰及び関係水路が一応竣功して以来、その維持、管理の為如何なる努力が払われてきたか古記録をたどってみよう。
竣功して一応通水はしたものの水乗りが充分でなく、末端の村では用水不足の声があって、堰の修理、補強をすると共に他の用水源よりの補水も考えられている。その間、筑前側からの抗議、妨害をも幾度となく受けるのである。以下主として「竹野郡床島堰所用水引請候新溝出来之儀委細書上候様に被仰付候に付申上候覚」(以下申上候覚という)を資料として述べよう。先ず新溝が出来たけれども水乗りがどうも充分でないので、古くからあった松木井手を1尺5寸(約50cm)嵩上げして、守部、八重亀の2ケ村を灌漑し、その他の地域はすべて床島用水掛りとしたが、井堰不備のため漏水が多く末端の村では水不足を生じた。そこで正徳4年午に、恵利堰に船通しがあっては多量の流水を逸するので、これを堰き止めて代わりに床島堰の少し上流の中洲の中央部分を掘り通して船通しとした。これが現在の船通しである。ところで、この船通し掘換えに際して筑前側からの執拗な妨害があった。そもそもこの中洲は筑後川本流と新溝に挟まれた河川敷内の島で、本来竹野郡早田村分だとされているが、丁度筑前領との境に当たり、境界も明確でなかった。筑前側としては恵利堰の船通しを堰き止めて流水を全部新溝に取り入れることになれば、筑前長田村附近一帯が湿田となり、且つ洪水の際は甚大な被害を受ける心配があるので、この掘換え工事に強く反対して妨害行為に出たものである。
まず、中洲は筑前領だと主張し、石材運搬船の通行を妨げるため乱杭を打ち込んで溝を塞いだり、筑前側の川岸に石堤(水刎)を築き、水勢を強くして恵利堰の崩壊を図ったりして妨害した。有馬側としては理を尽くして長田村の庄屋方へ度々掛け合いに行ったが、なかなか埒があかないので、強攻策に転じ、国老有馬要人初め藩役人達が現地を見分の上、この地は有馬領だということを確認して、総郡夫一日2,000人の人夫をもって、僅か3日間で工事を完了した。この工事の際の出来事であるが、ある日人夫の内に筑前の者6〜70人(この内には12〜3人の福岡藩士もいたらしい)が紛れ込んでいて、急に投石を始め、混雑にまぎれて早田村庄屋善左衛門を連れ去ってしまった。これは善左衛門が最も強硬に中洲の早田村分であることを主張していたためらしい。善左衛門は約3ヶ月間監禁され、その間厳しく責められて、無理矢理に詫び状を書かせようとしたが屈しなかった。結局、善左衛門は後述のような状況で帰るのであるが、後日この時の責苦が死因となったということである。善左衛門連れ去り事件について、有馬側は放って置いて何もしないので、筑前側はしびれを切らして和談を申し入れ、詫びを入れて帰したと言うことになっている。その後も恵利堰の修理、補強工事は続いているが紛争らしいものはなかった。ところが、享保20年(1735年)の春、筑前徳渕の大庄屋から塩足と北野の両大庄屋へ手紙で“恵利堰の嵩上げ工事があっている様だが、そんなことされたら筑前領15ケ村は湿田となるので止めてもらいたい”と言って来た。それで“嵩上げしているのではなくて、修繕しているのである”と返事をしたら、後は何もなく済んだ。翌元文元年にはまた、徳渕大庄屋から北野大庄屋へ、恵利堰の船通しを旧の通りにして古川筋(本流筋)を船が通れるようにしてくれるよう言ってきた。がこれまた、恵利堰は有馬藩領数千町歩を灌漑する重要な堰であるので、要求には応じられないと返事しただけで終わっている。同じ元文元年6月に出水の時、夜中に大勢の者が恵利堰を破壊しようとしたが、堰所番の床島村善右衛門父子の発見が早く、追っ払ったら筑前長田村へ逃げて行った。このような状況であるので、元文元年の暮れに藩では堰所番人の床島村善右衛門父子に鉄砲5丁と玉薬(火薬と玉)を持たせて警戒させることになった。
こうして床島堰を巡る筑前領との争いが飛び火して、大石村簗瀬堰をめぐる筑前・筑後の争いにも関連を持つようになっていくのである。すなわち、簗瀬堰の争いは床島堰での紛争の腹癒せに筑前側が仕掛けているのではないかという風説が立った。このことについて、その解決のため北野大庄屋秋山助蔵、十郎丸庄屋孫四郎、八重亀村庄屋九郎兵衛等は再三吉井へ出向いて生葉郡下の大庄屋、庄屋衆と話し合っている。最後には日田関村の佐平と日田豆田町の年寄三松久左衛門が調停役として奔走し、結局和解が成立する。いろいろと話し合った結果、ようやく誤解もとけ、簗瀬堰の争論は床島堰の遺恨でないことが明らかになった。かくして、長い紛争を経て、元文2年己(1737年)潤11月8日生葉郡高田村の境界争いも含めて、同時に高田村の現場で和解成立し、仲直りの杯を挙げた。現場に立ち会った稲数村庄屋中垣清右衛門は同日直ちに高田村から久留米へ帰り、和解の一件書類を藩庁へ提出して報告したところ、藩庁でも大いに喜んだ。
かくして、筑前領との争いの一部は床島堰竣功以来25年にして一応解決したことになる。しかしながら、床島堰渠設置の影響である筑前長田村附近の湿害については後々まで問題は残る。この件について有馬藩側の古記録によると、結局筑前側は湿害が甚大だと言っているがたいしたこともないようだというのである。
“暴れん坊”といわれる筑後川であるので、平素冷静な時においても御機嫌を損なわないよう気を配る必要があった。一度機嫌を損ねたら、何もかも破壊し尽くさねばおかないから始末におえないのである。正徳2年春堰渠竣功以来、施設の維持管理のためには相当長期間にわたって、多くの人夫と莫大な量の資材、費用を毎年定期的に投入せざるを得なかった。以下このことについて少々述べよう。まず、覚書について。この覚書は恐らく元文4年(1739年)に書かれたものであるが、それによると、まず、竣功の年、正徳2年から享保5年までの9年間は草野又六が堰渠の維持管理の総指揮者として夫役、資材その他経費の調達に当たっている。そのとき夫役は惣郡夫である。これが毎年続くので大変である。ちなみに惣(または総)郡夫とはいったいどれくらいの人数が集められたかは、このときの場合はわからないが、ここに同じく筑後川における大治水工事であった鯰久保川堀換の時の控えがあるので参考までに記しておく。この工事は丁度昭和年代に行われた小森野放水路(国道3号線久留米大橋より篠山城下まで)を掘り下げて本流にしたり、北野町大城橋から上流の放水路を本流にしたりして、流れの迂回蛇行を是正したのと全く同じ工事である。現在の北野町中島部落付近から筑後川本流が大きく右へ蛇行して今山部落(北野天満宮付近)付近を通って再び左へ急転し、鳥巣部落付近で現在の流れに戻っていたものを治水のため、享保10年、中島より鳥巣へ直通の新川を掘り換える工事である。そのとき惣郡夫でなされている。「鯰久保川掘替御普請入用夫目録」によると、12月1日から14日までの作業で総計27,445人の人夫を集めている。その内訳は、生葉・竹野・山本の上三郡から5,130人、三瀦郡4,321人、上妻郡3,089人、御井・御原郡14,905人となっている。最も工事の規模等で人数も異なるが、一般に惣郡夫は多人数を必要とする場合の夫役だから大同小異だと思える。遠く上妻郡、三瀦郡あたりから7〜8,000人の農民たちが歩いて、しかも筑後川を渡し船で渡って工事現場まで行くのは大変なことであったろう。
享保6年から8年までの3ヶ年間は毎年春の普請に約1万人ずつと、そのほかに常置の修理用の石材運搬船の乗組夫が、ほとんど年間を通して毎年40人ずつ。続く享保9年から13年までの5ヶ年間は、石船乗組夫は毎日50人になり、春の工事は、約1万人ずつを惣郡夫で就労させている。享保13年は筑後の百姓一揆があった年である。竣工後十数年にわたって、毎年毎年惣郡夫でいわば無報酬の強制労働が続けば受益地区以外からはそろそろ不平、不満の声が出ることである。これも又、一揆の一因となったのであろう。そこで次第に夫役の様相が変わってくる。
続く享保14年から18年までの5ヶ年間は惣郡夫を止めて溝下の受益村から石船要員を出している。そして享保15年5月には鵜川茂兵衛方で夫役のあり方について詮議がなされている。
それから9年後、元文4年(1739年)11月北野大庄屋秋山助蔵が御郡方、御検見方、御普請方北川某なる人へ送った書状の覚書がある。その内容は、かねて問題の役夫の件について、来年(元文5年)春の役夫削減の問題を、今回藩内25組の大庄屋が集まって協議した結果、床島井堰に関する工事の人夫は御井、御原両郡から出すようになったが、思えば床島井堰は広大な場所で且つ筑前との関係もあり、溝下の受益村々だけの出夫では微力なので、前々から江戸水道所より上流(多くの人夫を要するのはここの部分である)は惣郡夫に、水道所より下流は井掛役(受益村負担)と決まっていた。そして修理船5隻が年中作業を続けているほかに、春の工事には毎年1万人を越す人夫を惣郡夫にて就労させて、かろうじて井堰や水路の管理、維持を保っていた次第である。しかるに、去る享保15年戌年5月鵜川茂兵衛様方での協議で井掛役と定められ、享保18年まで4ヶ年間は溝下の村々だけで懸命にやってきたが、どうしても手に及ばず、井堰の破損も多く、事に去る享保20年の洪水の時は井堰の破損に対して早速溝下村より非常召集して堰止作業を始めたが、労力不足のため次第に破損個所が広まる気配があったので、御役人中様御見分の上、惣郡夫で修理を完了した。それ以後は再び惣郡夫となっているような次第である。床島堰は藩のためにも大切な場所で、溝下だけでは十分なる維持管理が出来ないのでよろしく惣郡夫に願いますというのである。
ところで、役夫削減の件について別人の覚書がもう一つある。内容は、前半は前述北野大庄屋の覚書とよく似ているが、後半において夫役の具体的な解決策を述べている。これは御井郡中村(
床島井堰の夫役は多数の人夫を要するので、初め惣郡夫によってなされていたが長くなるにつれて不平、不満を生じたため、井掛役に変更されたが微力で到底無理だから次のようにしたらどうかというのである。すなわち、床島用水の竣工によって4,000石以上の増収となり、これは藩全体の潤いとなる。従ってこの増収分の一部を常雇い人夫の賃米として、相当数の人夫を年中雇い入れ、維持管理に励めば堰渠は次第に堅固となる。というのである。その辺のことについて、こう書いている。増収4,118石とし、100石につき13俵にすれば535俵の代米となる。これを400俵(4人乗船石船5隻分20人給扶持米)、40俵(右材料2人給扶持米)、30俵(飯炊2人給扶持米)、65俵(その他雑)、という具体的な計算までしている。
以上長々と述べてきたが、要するに水の流れは絶え間なく、万全を期した工事でも、平和な平常時でさえ、いつの間にか底土をえぐられて崩れ落ちるのであるから、ひとたび大洪水ともなれば何もかも洗い流されるのである。年毎にやってくる災害に対して、ただ黙々として復旧作業に取り組んできた我々の祖先たちの長い間の苦闘はあまりにも大きな犠牲であり、尊い姿でもある。急流の筑後川の川底4町歩という広さに巨岩の石張りが定着するまでには長い年月を経ねばならなかったのである。
こうして守り通してきた堰渠であるので、少しでも妨害になるものを付近に近づけないために西と東の二カ所に制札が立てられていた。
さらに又、井堰を守るために井堰番を置いて鉄砲までも配備されていたことは前述したとおりである。
5 堰渠の構造と系統
通称床島堰というのは三つの堰から構成されている。筑後川本流に設けられているのを恵利堰と言い、中洲の東突端(最上流部分)から左岸浮羽郡田主丸恵利部落の川岸までの間を堰き止めたものである。この堰によってたたえられた水を右岸(北川)沿いに幅約28間(約50メートル)の溝を掘り、西方,2197間(約4キロ)の地点江戸部落まで導き、ここに設けられた水道をくぐり北水道(下郷用水)(長さ12間、横6尺5寸、高さ6尺)、南水道(上郷用水)(長さ12間、横6尺5寸、高さ6尺)を経てそれぞれ遠く末端部落まで灌漑するのである。中洲の突端(頭首口)より下流約550間(約1,000メートル)付近の南岸に床島堰(百間堰ともいう)が設けられている。この堰は流れを堰き止めるのではなくて溝岸の一部をなし、上口幅72間(約13メートル)、下口幅66間(約120メートル)、長さ36間(約65メートル)の全部石畳式で普通の溝岸の高さより少し低くしてある。従って、増水の時は堰を越えて筑後川本流へ流れ込むので、岸の他の部分を侵されることはない。いわば放水路の役を果たす施設である。それから更に下流240間(約436メートル)南岸には佐田堰がある。この堰は前述のごとく佐田川をせき止めて用水路へ合流させるためのものであったが現在は用水路の上を流れて本流へ流入している。
恵利堰は中洲の東突端から恵利部落の方向へ至る恵利瀬といわれる部分に築かれている。
この堰が本堰とも言うべきものであり、総称する場合、恵利堰というのが至当のようだが、従来から床島堰と総称している。これは旧藩時代恵利堰付近が筑前領との境にあるので紛争の発生を恐れてのためであったらしい。工事の際困難を極めたのはこの堰である。
恵利堰の現地に立っている「水利使用標識」によると、本堰の取水量は頭首口地点で、7.7立方メートル/秒となっているが、土地改良区が作成している水系別配水量図によると27立方メートル/秒、灌漑面積は2,700ヘクタールとなっている。又、「堰の流れ」、その他では3,000町歩(約3,000ヘクタール)になっているが、土地改良区の資料によると昭和47年現在、約2,000町歩(約2,000ヘクタール)である。受益地域の末端は遠く西鉄大牟田線
前述のごとく広大な灌漑面積ではあるが水量は豊富で末端の隅々まで充分行き届いている(特殊事情により部分的には2〜3の例外はある。この点は後述する)。恵利堰発端の頭首口より江戸水道までは幅広い直線の幹線水路が一本通り、はるか後年になって設けられた鳥飼揚水機(明治45年)による分水と、西原水路及び徳次水路(対象2年6月)の支線が分岐して付近一帯を灌漑している。水路は江戸前で小石原川の底を潜り(サイホン式)大堰神社の真裏にいったん現れて、神社の両側(北と南)にわかれ、直ちにそれぞれ北水道、南水道をくぐり抜けて、一つは北水路、他は南水路となって流下するのである。北水路は大刀洗小島、春日、平田、甲条方面へ流れる四ヶ村水路が分岐し、幹線は北回りではるか西方地区を灌漑している。すなわち、北野町では陣屋川堤防の西側一帯(旧弓削村の西半分を含む)、小郡市の一部及び久留米市宮の陣地区の全域を灌漑する。南水路は水道を出て直ちに南進し、八重亀で西へ方向を転じ、筑後川堤防沿いにやや南寄りに西進し、北野町の旧金島村、大城村地区の全域と旧弓削村の東半分を灌漑する。
6 堰渠の管理運営
床島堰渠の管理は藩政時代に置いては藩の管理下にあったが、明治4年7月1日廃藩置県により郡役所の管理となり、大正13年5月1日「江戸水道以上用水組合」を設立し、郡役所より管理を引き継いだ。昭和30年8月1日江戸水道以上用水組合を三井郡床島堰土地改良区と改称し、昭和34年1月1日水道以下の用水組合(大堰村外二ケ村用水組合、北野町上二ケ村用水組合、北野町下二ケ村用水組合)を合併し、昭和38年4月1日三用水組合(宮の陣用水組合、赤川用水組合、平方用水組合)を合併して今日に至っている。
水量は恵利堰によって筑後川の流水を取り入れているので豊富であり、少々の干ばつ時でも灌漑に支障を来すようなことはない、といわれている。もっとも部分的には漏水、高地、末端等の理由で灌漑水が十分に行き届かない地域もあり、ある時期には用水機等によって補水しているところもある。本改良区が作成した問題点の数例を以下に示そう。
(1) 恵利堰より江戸水道までの水路においては、特に頭首口より鳥飼水門までの間は筑後川の河川敷内にあって土水路のため漏水が多く、筑後川の水を全量取り入れているので平常で27立米/秒以上あるにもかかわらず、鳥飼で16〜18立米/秒となる。平常水の場合は差し支えないとされているが長期干ばつ時においては水不足が心配である。
(2) 南水路は富多部落を出る頃から灌漑され、金操の遊水池で守部水路が分かれて堤防下の地域を灌漑しつつ、必要箇所には支流を持って隅々まで水田を潤している。しかしながらこの線は比較的標高が高く、しかも、土水路のため末端においては年々水不足を来すことがあり、干ばつ時にはいち早く困る。
(3) 北水路では宮之陣地区の樽角、三条付近は末端であり、且つ筑後川沿いの高地でもあるので水の不足を来たし、揚水機による補水が行われている。
(4) 赤川水路は
以上の他にも諸処の問題はあるが、いずれもそれほど重大な問題ではない。
7 恩賞の願書
床島堰渠竣工直後、本庄主計父子が建設の功労者6名を自宅に呼んで、慰労かたがた感謝の意を表したことは前述したが、そのとき呼ばれた6名は、普請奉行野村宗之丞、普請惣才判草野又六、北野大庄屋秋山善左衛門、稲数村庄屋中垣清右衛門、八重亀村庄屋秋山新左衛門、
後年、文化14年(1817年)樺島石梁による床島石碑では藩役人野村宗丞、草野又六の他は稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門、
明治19年6月福岡県令より金30円を賜って追賞があった。このときの受賞者は草野又六、
大正5年秋陸軍特別大演習の際11月15日付けで従五位の追贈がなされた。このときは前記5名の他に早田村庄屋丸林善左衛門を加えて6名になっている。
大正14年11月29日大堰神社に合祀された、草野又六、高山六右衛門、秋山新左衛門、中垣清右衛門、鹿毛甚右衛門、丸林善左衛門の6名である。井掛村住民の子孫たちが早田村庄屋丸林善左衛門の犠牲的功績に対して感謝の意を表したことが伺える。
床島堰渠については次の2つの文がある。1つは安永6年(1777年)7月久徳新七の撰になる「床島堰記」、と他は文化14年3月樺島石梁の撰になる「床島石碑」である。
※ 以上、九州農政局筑後川水系農業水利調査事務所が昭和52年3月作成した「筑後川農業水利誌」を参考