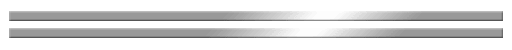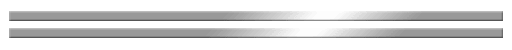magi-4
大堰神社
碑 文
修復再建碑文
江戸時代中期(1700年代初)筑後川北岸一帯の地は美田であったものの水利に乏しく干害も甚だしく、宝永7年(1710)の旱魃に遭遇することで居民は離散する者が多く、村は年々疲弊していった。
当時の庄屋高山六右ヱ門を始め、秋山新左ヱ門、鹿毛甚左ヱ門、中垣清右ヱ門らは皆郷土を守り村民を救助せんとして、河北水道を開削することで灌漑の途を開こうと決意し、久留米藩府に嘆願して許可をうけ、藩府の命により、草野又六が指揮官として任に当たった。
まず、石垣を正徳2年(1712)正月21日をもって起工し、日に3千5百人の人夫を擁して、遮断と填築にかかったが、筑後川のこの一帯は名に負う奔流の地で、工事の様子を、当時の藩の家老は「勇壮にして活発、観る者の魂を奪われ、前代未聞の壮観なり」と激賞したほど、壮絶な、流れとの戦いであった。
同年2月晦日ようやく石垣が成就した。そこには当時、水利の問題で筑前藩との争いがあったが、庄屋丸林善左衛門は身を呈して大堰完成に寄与していたことが後に判明した。
以後、新水道の開削等工事をなし、同年4月13日床島堰及び新水道の竣工がなったものである。
こうした偉業は以後渠下万民が生命の恩士として崇敬するところとなり、古来、年々歳々、村民集いて、先人への謝恩を表し、露天にて祭典を営んできたが、関係諸町村民(現2市2町)がこれを遺憾として、神殿に祭祀すべく彰徳会を組織し、時の政府に請願してきた。大正5年、この偉業は時の天皇にも追賞せらるるところとなり、同14年11月29日、当時、村社天満神社、無格社水神社と合祀することで大堰神社に祭祀されたものである。
以来70有余年、大堰神社は氏子、崇敬者により赤誠の念厚く護持されてきたが、今度の国営最終事業の中で、用水路が境内地の直下を通る事となり氏子及び関係者に強力の要請があった。去る平成3年の台風により社殿の被害を受けた事も勘案し、この事業に積極的に協力する事に致し、ここに社殿全てを解体するに至った。
修復に当たって、歴史ある資材はできるだけ使用し、忠実に復元したものである。
なお、狛犬、撫牛も同時に再建造することで崇敬の念を新たにし、地域の興隆と平穏無事を祈願するものである。